- 技術士二次試験はどういう対策した?
- 出願時に提出する経歴書の記載の留意点は?
- どんな論文テーマを予想してた?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士を目指して合格に至った経緯を体験をもとに綴っていきます。



二次試験対策が本格化!

2011年の年明けとともに、初の二次試験に向け、準備を本格化させていきました。技術士の書籍を読んだり、スクールに通ったりしていました。スクールでは、ガイダンスで試験の概要の説明が行われ、その後、建設部門の担当講師による講義が行われました。スクールでは、スクーリング5回と添削5回のコースでした。当時は、Web会議システムなどもなく、その都度東京へ通いました。早朝に自宅を出て、昼前から夕方まで講義を受け、夜中に帰ってくる、丸一日コースでした。
必須論文や選択論文も学習しなければなりませんが、まずは経歴書を整理する必要がありました。4月の出願時点で経歴書の提出が必要です。現行制度とは異なり、体験論文(3000字以内)は、筆記試験合格後に提出するル‐ルでした。それでも、業務経歴書の詳細欄に題目を記載する必要があったので、テーマと構想程度は練っておく必要がありました。
経歴書の書き方

現行方式と異なる体験論文ですので、詳細は割愛しますが、積算システムの構築をテ‐マにし、構想を考えていました。経歴は、一般的に書くなら、「共同住宅や生産施設の施工管理や積算の業務」となるわけですが、技術士にふさわしい経歴でなければなりません。私も当時のS先生に赤ペンでびっしりと指摘されましたが、技術士法の第2条を確認しておく必要があります。
(技術士法第2条 一部抜粋)
個人的には、合格した年度の口頭試験前に、相当回数の復唱を行い丸暗記したので、いまだに頭にこびりついている文言です。特に、アンダーラインを引いた項目を経歴に反映させる必要があります。私の場合なら、以下の具合になります。
- 施工管理→施工計画
- 積算→コスト分析あるいはコスト設計
最初は、違和感を憶えました。「自分は、本当にこんな業務を今までやってきたか…?」と。ですが、その違和感こそが、現状レベルと技術士レベルの差そのものでした。納期までにまとめるだけで精一杯で日々追われていた業務。技術士として、本来ならば、どこに着目すべきなのか、どこに力点を置くべきなのか。試行錯誤を経ながらも、自らの業務を見つめなおす習慣が芽生えていったと思います。
準備期間中にとんでもない出来事が…
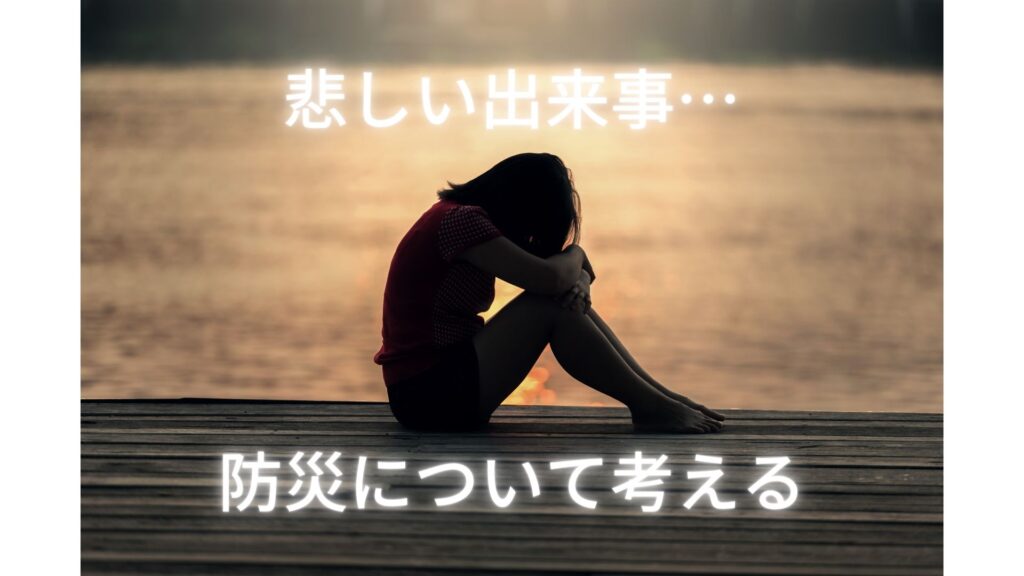
翌日には、東京のスク‐リングが控えていましたが、延期となりました。その東京でも天井の落下や停電などの被害が生じていました。S先生のご親族のお住まいが東北地方に近く、被災されたとも伺いました。被災地の悲惨な状況が日々報道され、日本中が悲しみと自粛ム‐ドに包まれていた、あの時期です。
数日後、東京では最低限の交通網は復旧し、延期されていたスク‐リングが開催されました。驚いたことにS先生は、以前と変わらず、教壇に立ち熱い指導をなさっていました。論文の添削にしても、それまでと変わらないスピ‐ドで返送されてきました。また、技術士建設部門の必須論文として、この震災をテ‐マにした問題が出題されるかもしれないとの事でした。
 Kay
Kayそれまでの災害デ‐タを基に構造物を設計して造るだけでは、今回の津波は防ぎようがない…。



ハ‐ド・ソフト両面を踏まえた多重防御で対抗するしかない…。



建築物であれば、建設すべき場所や構造はどうする…。
論文試験という枠を超えて、いろいろと防災について考えさせられる契機になっていました。他にも、低炭素化社会、維持管理、技術開発、地域活性化、建設業のコスト構造改革などのテ‐マの論文作成に取り組み、テ‐マを一覧表にまとめる作業を行っていました。
当時の選択論文は、現行とはかなり方式が異なっていました。なので、詳細には触れませんが、15問出題される中から2問を選んで、それぞれ3枚の回答用紙にまとめるものでした。受験者の得意な分野の問題を選べる方式でした。私は、入札契約と原価管理分野に絞り、準備を進めていました。
まとめ
- 初年度は、二次試験対策としてスクーリング&論文添削のコースに通っていました。
- 経歴書は、技術士に相応しくするために技術士法第2条の項目を確認しましょう。
- 世の中の出来事がテーマになりえます。試験の枠組みを超えて考えてみましょう。
次回は…


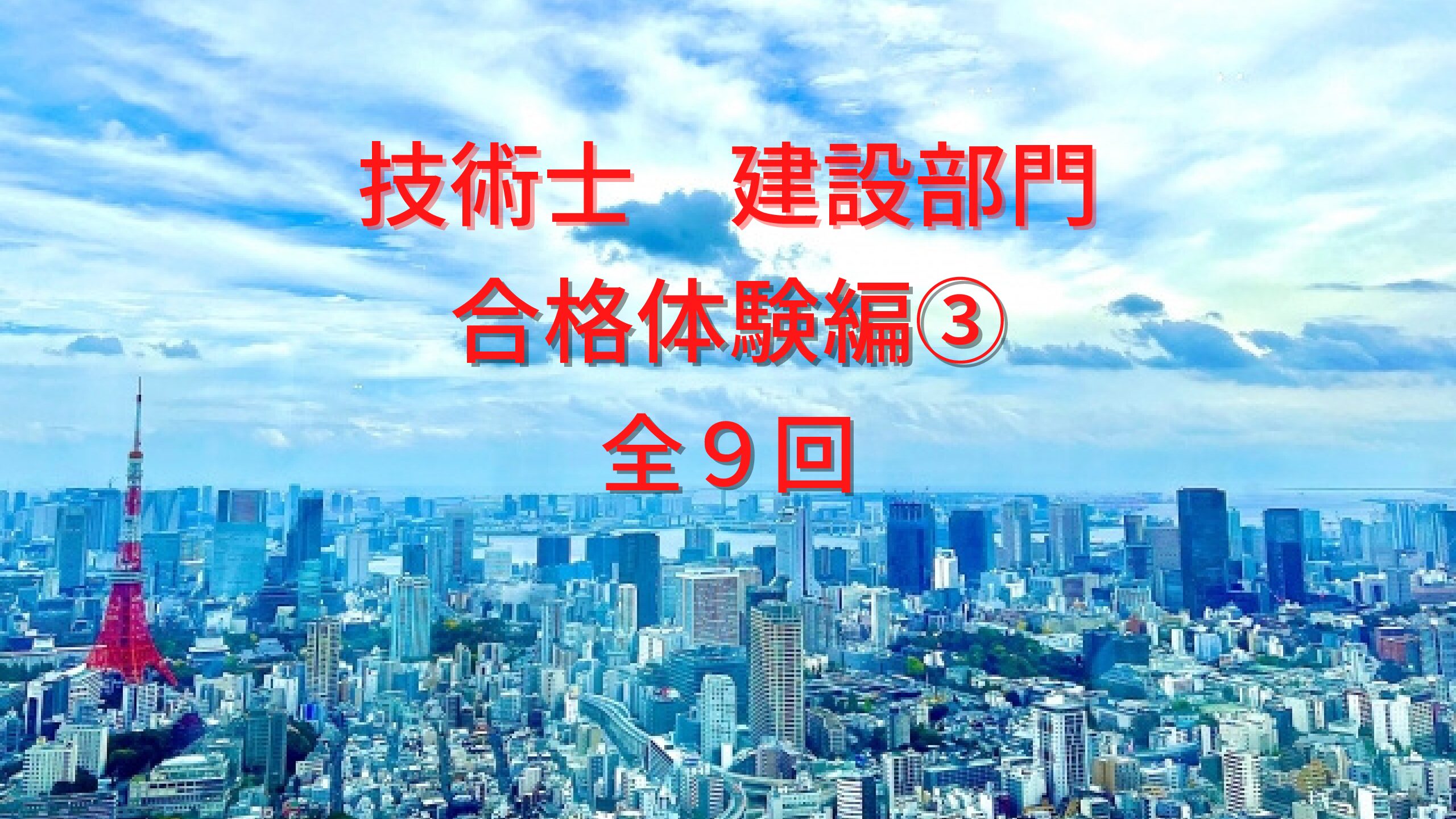

コメント