- 初の二次試験の本番はどんな状況だった?
- やってはいけない論文の回答とは?
- 初挑戦の合否結果は?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士を目指して合格に至った経緯を体験をもとに綴っていきます。



初の二次試験本番へ

まずは、午前の必須論文。
出題テ‐マの一つは、社会資本整備全般について、もう一つは、建設産業の活力回復について。
 Kay
Kayうーん、どちらも用意していたテ‐マとは違う…。
とりあえず後者を選択し、なんとか用意していた回答パタ‐ンにこじつける形で、回答用紙3枚を書き切りました。
午後は選択論文です。
出題15問のうち、まずは自分の得意な分野の問題を探しました。例年なら3題は答えられます。しかし、期待していた入札契約の問題ですが、聞いたこともない方式がテ‐マとして出題され、スル‐するほかありませんでした。必然的に選択の余地もなく、2問に答える形になってしまいました。原価管理の問題も、土木の原価管理の実際の業務の流れを説明する問題で四苦八苦しました。



それでも3枚書き切る!
当時の試験終了後の感想を正直に書けば、こんな感じです。



想定とはだいぶ違う出題がされて、回答は強引だったかもしれない。
でも、書き切ったし合格の可能性もそれなりにあるかな…
今の私の視点で試験を総括
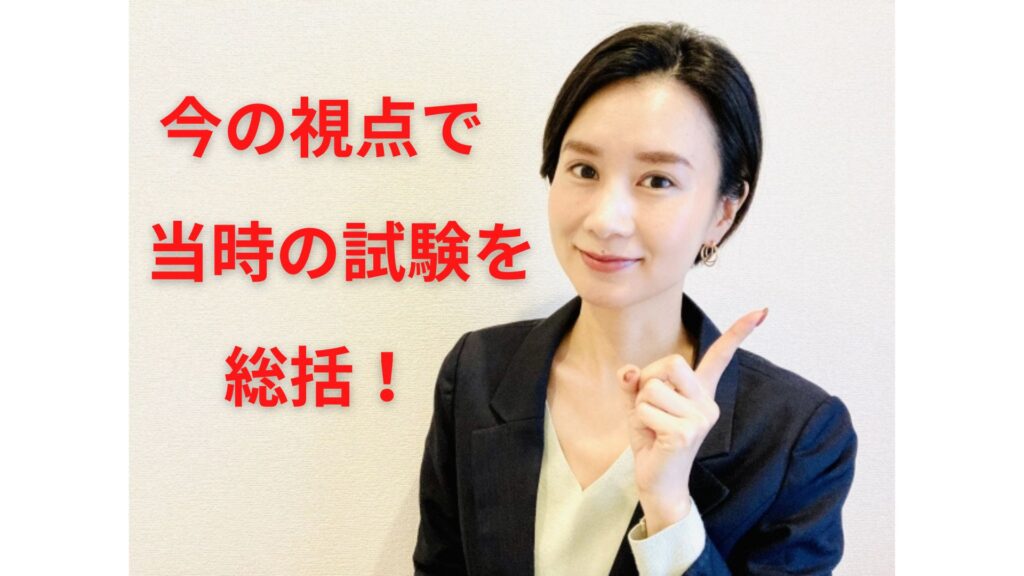
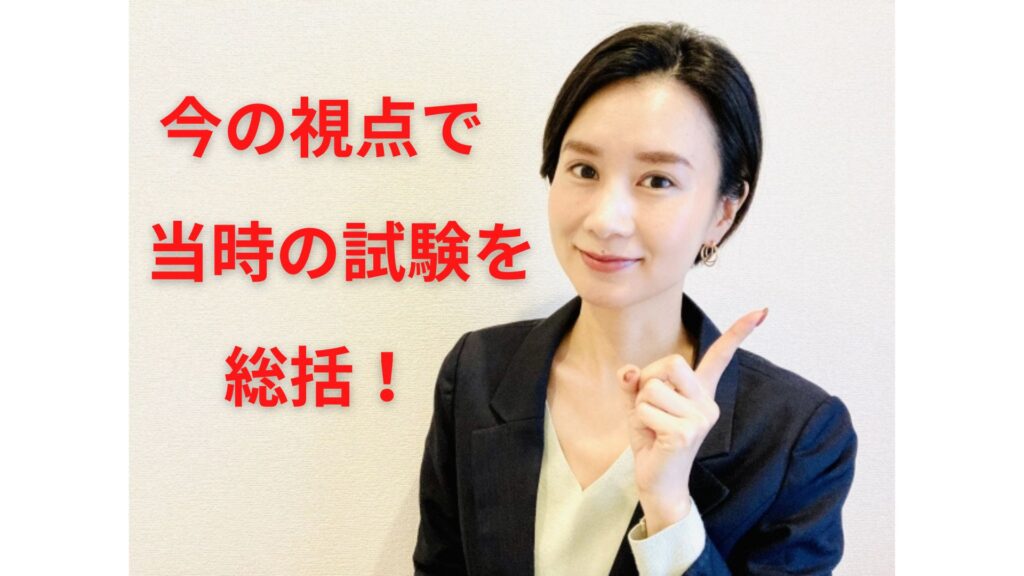
当時の復元論文はありますが、とても本ブログで掲載できる水準にありません。読んでいただいている皆さまの貴重な時間を無駄に奪ってしまいます。例えば、必須問題では、建設産業の構造自体が問われているのに、なぜかコンパクトシティが回答に書かれておりました。選択論文の土木の原価管理にしても、土木学会が定義している3項目の文言が一つも書かれていません。
そんな事も分からず、いくばかの合格の可能性を信じて、筆記試験後も体験論文の推敲に励んでおりました。
そして合格発表、私の受験番号は…
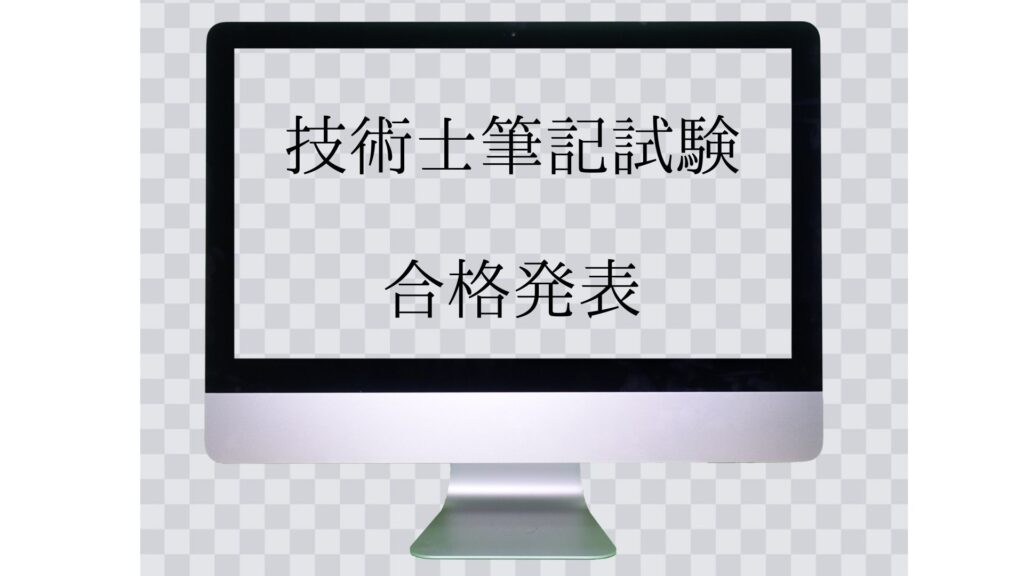
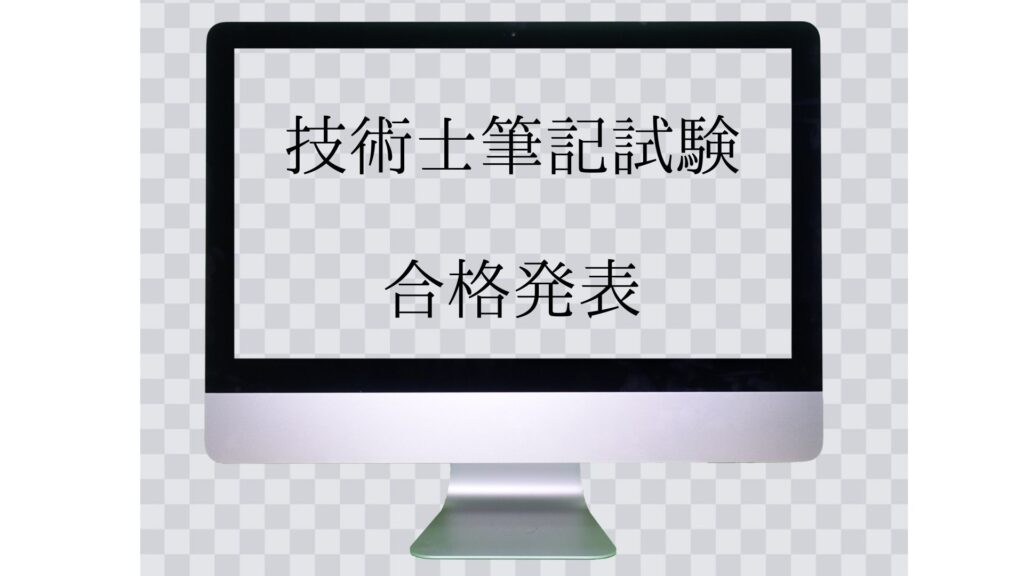
秋が深まっていく10月下旬、二次筆記の合格発表日です。筆記試験以降、この日を忘れる事はなく、当時の私にとって何より重要な日でした。合格発表日が近づくほど、ソワソワしておりました。これでも年明け以降、毎朝5時前に起床して勉強してきた訳ですので…。前日の夜は眠りにつけませんでした。技術士の某インタ‐ネット掲示板では、いつも活発な議論がなされておりましたが、発表前夜ともなると、ことさら盛り上がっていたように思います。
合格発表日の早朝、技術士会のHPにて、合格者の受験番号が公開されます。正確な発表時刻が公表されている訳ではないので、例年だと何時ごろだとかの情報は某掲示板から得ていました。浅い眠りに落ちては、目を覚ます。この繰り返し…。朝5時半くらいだったでしょうか。
掲示板コメント出現 「出ました!合格しました!」
えっ?…
急ぎ技術士会のHPへ…!
最新情報欄に「二次試験合格発表」の項目が…!
PDFファイルをクリック…!
建設部門…!
施工計画…!
地域別のアルファベット…!
番号…
…
…しばらく時間が止まっていました。



ふーん…
そう…
落ちたの…
ああそう…
へぇー…
そうなんだー…
掲示板の「合格しました」スレッドが10個20個と増えていくのを、無感覚にただ見つめていました。
その日、会社には、



前後賞を獲得しました
…と報告しました。
…これが精一杯のジョークでした。
こうして、技術士二次試験の1年目の挑戦は終わっていきました。
まとめ
- 想定外の問題が出るも強引に書き切って試験を終え、なぜか一定の手応え
- 今の視点で言えば、その当時の論文はブログで再現する水準にあらず…
- 合格発表の結果、自分の受験番号は前後賞…
次回は…




コメント