- 建築の経歴でも技術士(建設部門)を取得できる?
- 建築関係者が今後取得したいのは技術士?
- 技術士一次試験はどうやって乗り越えた?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士を目指して合格に至った経緯を体験をもとに綴っていきます。



技術士建設部門に建築科目はないが…

21部門の一つに建設部門があります。
名前が似通っているので混同されがちですが、「建設」とは、対象を土木構造物や建築物を包括しています。一方、技術士建設部門の中には11科目がありますが、その中に建築という科目はありません。河川・砂防・海岸・海洋、空港・港湾、道路、電力土木、鉄道、トンネルなど、土木に関連した科目がずらりと並んでいます。
建築専門の方にとって、技術士に関心があっても、受験をためらう要因があるとすれば、この辺りの実情ではないでしょうか。私も当初は、そもそも経歴として自分が技術士を受ける要件を満たしているのか疑問でした。二次の過去問を見ると、不安がさらに助長されます。設問に出てくるのが土木構造物ばかり…。
結論から言えば、受験の要件としては、建築の経歴でも問題ないです。現に、私以外にも建築分野から技術士になられた方は一定数います。ただし、ある程度、土木と建築の共通項だけでなく、土木そのものの学習が必要とは思います。例えば、コンクリートの管理基準をとっても、建築のJASS5と土木の示方書では相違点もあります。したがいまして、多少のハンディはあるものの、挑戦できる環境にあるのだ、という認識で良いかと思います。
建築関係者への『今後取得したい資格』アンケート!

2022年5月の日経ア‐キテクチュアの記事によれば、建築関係者322人にアンケ‐トをし、今後取得したい資格として、以下の結果が出ています。
アンケート対象者が建築関係者なので、すでに一級建築士を保有している方が一定数いるとはいえ、技術士が2番手にランクインするのは意外でした。技術士の一般認知度が低いと先ほど申しましたが、この結果を見る限り、建築界隈では必ずしもそうでもないことになりますね。個人的にも、建築関係の方々が技術士を取得する流れは、世のためにも良いことと思います。
最初の関門、技術士一次試験!

話がそれましたが、一次試験は2010年の秋に受験しました。試験方式は、現行と同じく択一式ですが、合格基準が若干異なっていました。それぞれに足切り点が設定されながらも、基礎科目と専門科目は合計点で評価される方式でした。今の方式は、基礎・専門・適正、各々全科目で合格点を超える必要があります。
基本的な対策としては、わりと過去と同様の出題がなされているので、とにかく過去問を解いて解説を読んで納得する、の繰り返しを行いました。適正は、それに加えて最近の技術関連の不祥事などのトピックも整理しました。
基礎科目は出題範囲が広いので、捨てる分野も決めておいた方が、学習効率の意味では良いです。私は、早々に化学と生物の問題は捨てる事を決めました。(現行方式は、基礎と専門の合算ではないので、やや慎重に構える必要はありますが…。)
正直、当時の一次試験の記録はあまり残っていないのですが、いずれの科目も65~75%の得点率だったと思います。
クリスマスの時期に合格発表があり、
その年の一次の合格率は、例年より低く、約20%でした。
まとめ
- 建築の経歴でも、技術士建設部門の受験は可能
- 建築関係者で技術士(建設部門)を取得したい人はそれなりにいる
- 技術士一次試験は、過去問を繰り返しプラスαの戦略(トピックの整理、捨てる範囲の検討)があると良い
次回は…
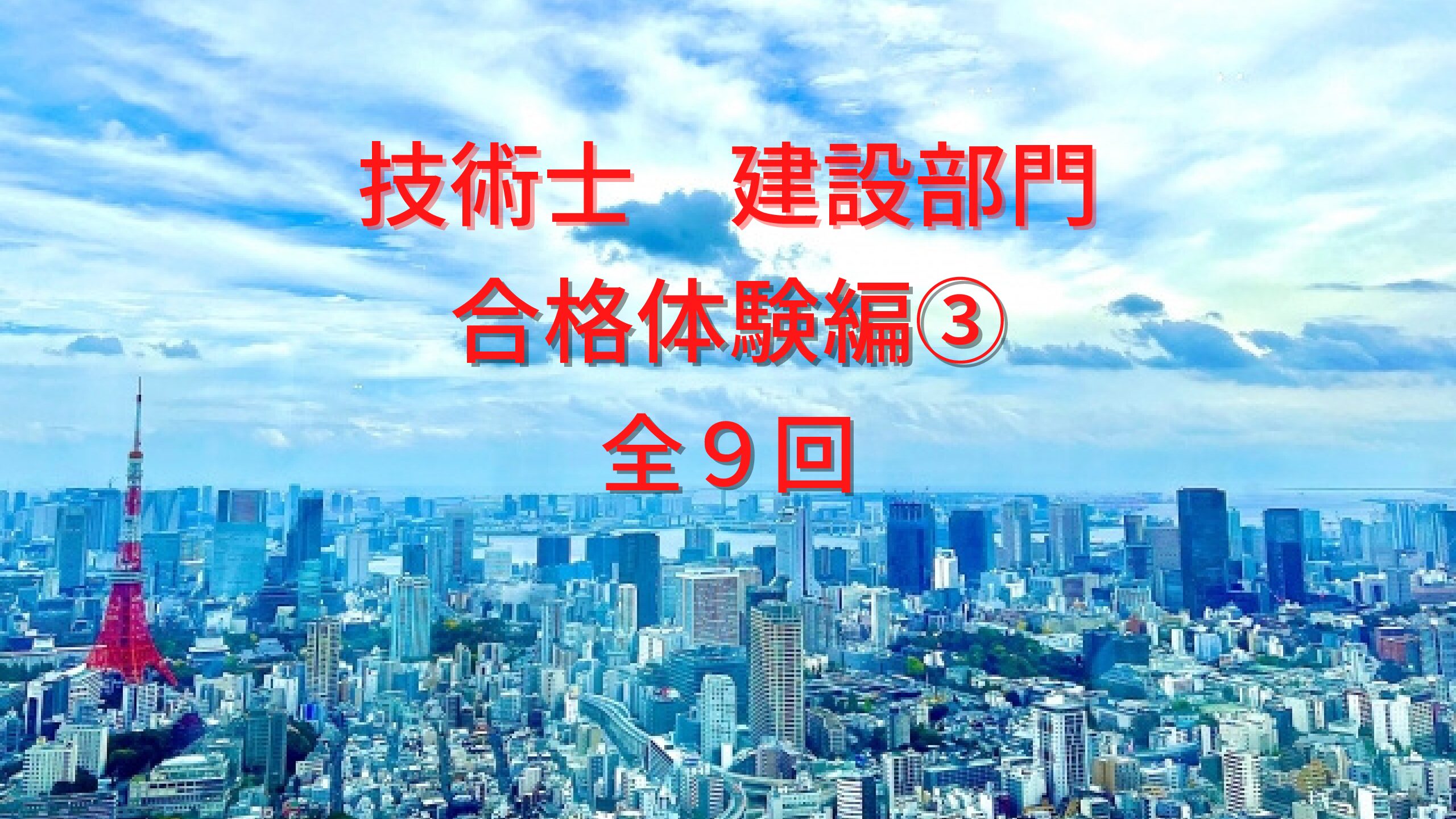
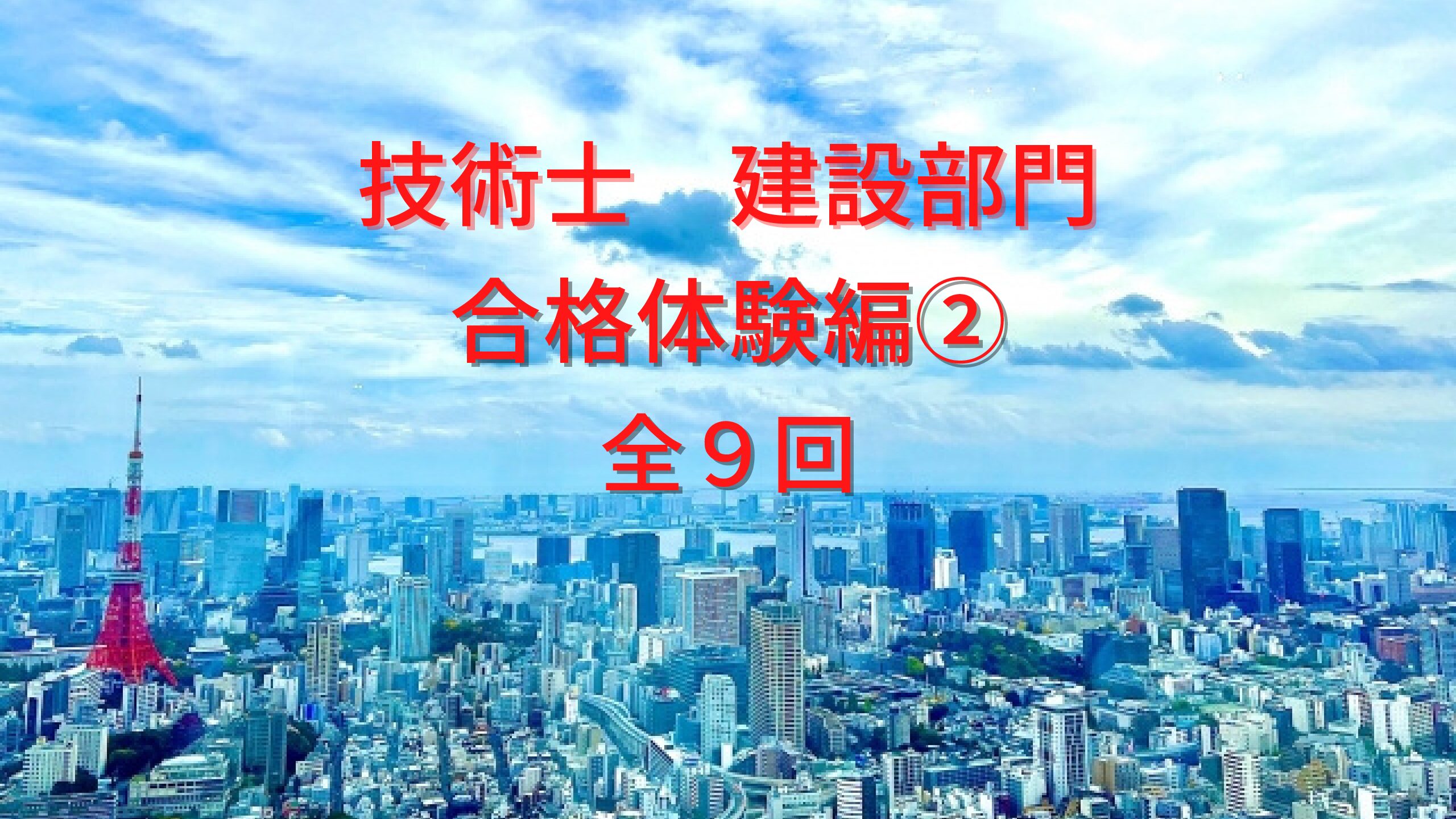

コメント