- メンテナンスの課題とは?
- 最も重要な課題に対する解決策は?
- 二次リスクへの対応は?
- Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の問題に斬り込み、回答要点を発信していきます。




建設部門(施工計画)/2020年/必須Ⅰ/試験問題

今回は、必須の2020年です。出題テーマは、メンテナンスです。
問いかけの切り口となっている部分にアンダーラインをしておきます。問いかけの切り口についての解説は以下の記事をご参照ください。

2020年 必須 Ⅰ‐2
我が国の社会インフラは高度経済成長期に集中的に整備され、建設後50年以上経過する施設の割合が今後加速度的に高くなる見込みであり、急速な老朽化に伴う不具合の顕在化が懸念されている。また、高度経済成長期と比べて、我が国の社会・経済情勢も大きく変化している。
こうした状況下で、社会インフラの整備によってもたらされる恩恵を次世代へも確実に継承するためには、戦略的なメンテナンスが必要不可欠であることを踏まえ、以下の問いに答えよ。
(1)社会・経済情勢が変化する中、老朽化する社会インフラの戦略的なメンテナンスを推進するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し、その内容を観点とともに示せ。
(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
(3)(2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。
(4)(1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。
建設部門(施工計画)/2020年/必須Ⅰ/回答要点
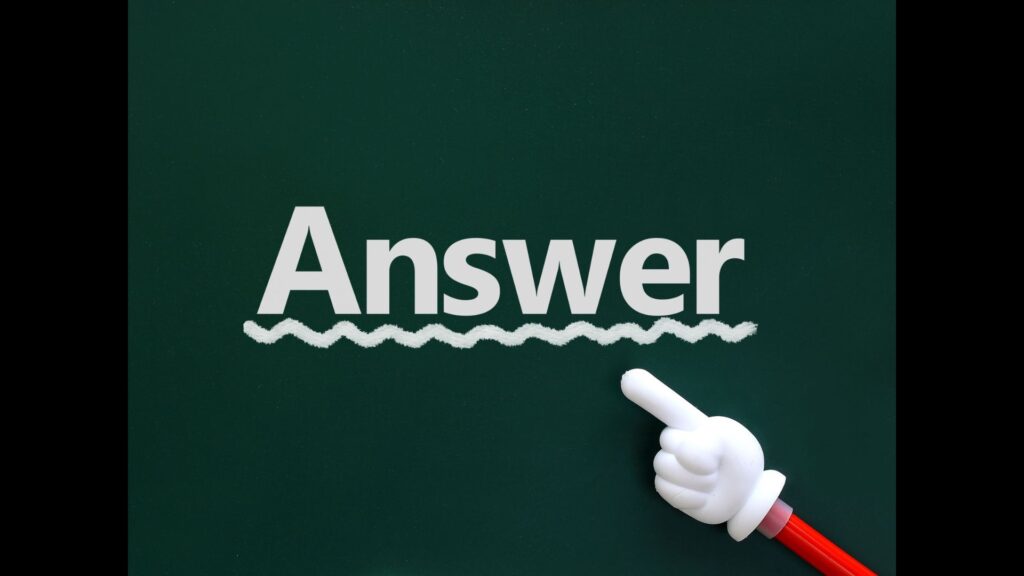
回 答 要 点
(1)課題
①メンテナンス手法の確立: 2040年には道路橋75%、砂防えん堤71%、港湾施設66%が建設後50年超。劣化進行による崩壊リスク有。点検、補修方法に個人差。
②メンテナンス費用の捻出: 少子高齢化による税収減。有限である財源を効率的に活用する必要性。従来の維持管理の発注方式では資金面で不合理なケ‐ス有。
③メンテナンス人員の確保: 建設人口の減少、学生の建設業入職離れ、高齢化の進行。メンテナンス知識を持った人材の不足。
(2)最も重要な課題:メンテナンス手法の確立
解決策
①システムの整備:メンテナンスのマネジメントサイクル(点検、補修、記録、新設事業へフィ‐ドバック)の仕組化、デ‐タベ‐ス活用(インフラメンテナンス2.0、xROAD等)。
②社会資本と技術者のレベル区分:当該社会資本が担っている機能や重要度、供用規制の難度、迂回の可否などを勘案し、社会資本毎の管理レベルを設定。点検者及び診断者の技術能力と責任を明確化する資格制度を確立。
③技術開発の推進:画像計測、非破壊検査、モニタリングなど、ITやAIを駆使した点検技術や、劣化予測技術、補修・補強技術の開発を推進。
(3)新たに生じるリスク: 地域格差の発生→財政難や人材不足の自治体で取組み進捗が遅れるリスク
対応策: 技術拠点の整備→地方ブロックごとに拠点を整備。中央拠点から、専門技術者の育成やプラットフォ‐ムを活用した最新の情報共有などの技術支援。包括的発注による維持管理体制の柔軟化。
(4)必要となる要件:メンテナンス技術をはじめとした継続研さんを行い、住宅および社会資本の適切な維持管理を通じて社会の持続可能性の確立、ひいては公益確保に貢献。
次回、2019年をお見せします…


コメント