- 入札・契約の適正化に向けた課題解決策とは?
- 新たに生じるリスクとその対応策とは?
- Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の問題に斬り込み、回答要点を発信していきます。




建設部門(施工計画)/2021年/選択Ⅲ/試験問題
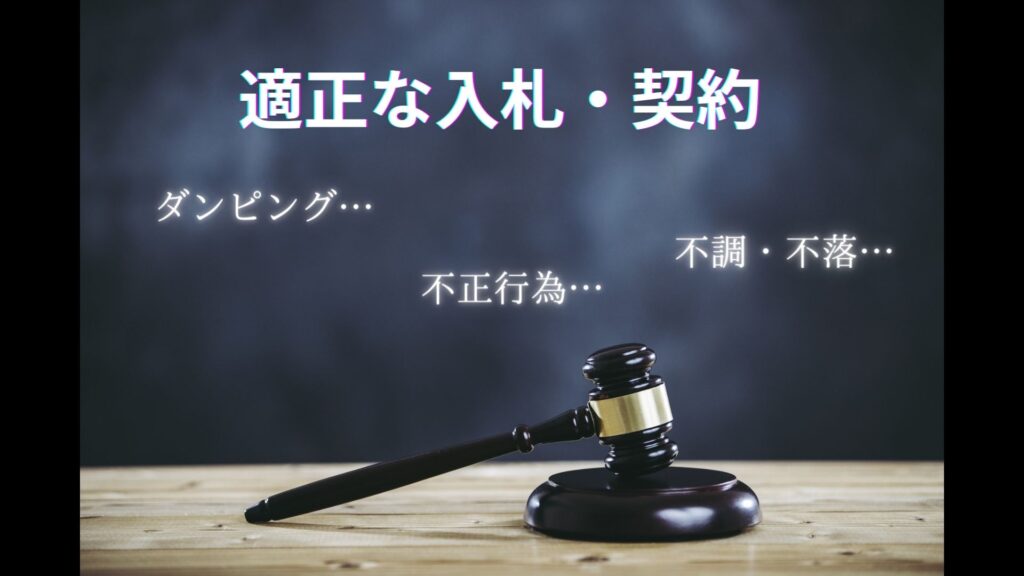
今回は、2021年の問題について要点を答えていきます。ぜひ、ご覧ください。
2021年 選択 Ⅲ‐2
公共工事の入札・契約では、透明性の確保、競争の公正性の確保、入札談合などの不正行為の排除、ダンピング受注の防止、不調・不落対策などの入札・契約の適正化が求められる。
発注者においては、ダンピング受注を防止するための適切な低入札価格調査基準や最低制限価格の設定と、不調・不落対策などに対応するため適切な発注が求められている。一方、応札者は、発注者が設定する予定価格および低入札価格調査基準などを推算し、応札している実態も指摘されている。
このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。
(1)公共工事が、適正な額で応札・落札されるための課題について、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題の解決策を複数示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
建設部門(施工計画)/2021年/選択Ⅲ/回答要点

回 答 要 点
(1)課題
①適切な入札・契約の執行: 1)国や都道府県レベルでは総合評価方式の運用が定着しているが、小規模自治体では単純な価格競争方式に依存する実態も 2)簡易的な総合評価方式だけでは適正額での選定が困難なケ‐ス有→工事目的物の特性や完成期限に応じた適切な方式でなければ、成立しない恐れ。
⓶適切な官積算の実施: 1)過去に同種の実績の少ない特殊性の高い工事ほど、官積算と応札額との金額乖離が生じやすい→不落の発生や、全応札者が最低制限価格を下回る恐れ。2)単調な工事ほど、応札者が官積算価格を推測しやすい→入札が価格当てゲ‐ムに陥る。
③適切な入札参加要件の設定:不良不適格業者が入札に参入できてしまうと、ダンピングの懸念。落札してしまうと、品質不良や工期遅延、労災、不透明な追加費用要求の懸念が高まる。
(2)最も重要な課題: ①適切な入札契約の執行
解決策
①発注者支援: CMrを起用し工事特性に応じた入札契約方式を選定。設計や官積算の監修、応札者の総合評価なども対応。特に、専門的人材が限られる地方自治体などで有効に活用。
⓶交渉方式の採用: 難度や期間制約の高い工事の場合は、公募で技術提案によって業者を選定し、のちに個別に価格を交渉・決定する。設計・施工一括発注方式やECI方式など。
③支払い方式の検討:特殊性の高い工事では、オ‐プンブック方式で協力業者の実質コストも可視化。コストプラスフィ‐による契約→コストの透明性が高まる。
(3)新たに生じるリスク: 多様な入札・契約方式により、民間の固有技術を円滑に活用しやすくなる反面、コストや性能の客観性に疑問が生じる。
対応策: 固有技術にはエビデンス徴収し、専門性ある第三者による客観評価。
次回、2020年の問題を…


コメント