- 風水害対策の課題とは?
- 最も重要な課題に対する解決策は?
- 二次リスクへの対応は?
Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の問題に斬り込み、回答要点を発信していきます。




2021年/必須Ⅰ/試験問題

まだまだ記憶に新しい2021年の必須Ⅰ-2の問題を掲載します。出題テーマは風水害対策です。
問いかけの切り口となっている部分にアンダーラインをしておきます。問いかけの切り口についての解説は以下の記事をご参照ください。

2021年 必須 Ⅰ‐2
近年、災害が激甚化・頻発化し、特に、梅雨や台風時期の風水害(降雨、強風、高潮・波浪による災害)が毎年のように発生しており、全国各地の陸海域で、土木施設、交通施設や住民の生活基盤に甚大な被害をもたらしている。こうした状況の下、国民の命と暮らし、経済活動を守るためには、これまで以上に、新たな取り組みを加えた幅広い対策を行うことが急務となっている。
(1)災害が激甚化・頻発化する中で、風水害による被害を、新たな取り組みを加えた幅広い対策により防止または軽減するために、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。
2021年/必須Ⅰ/回答要点
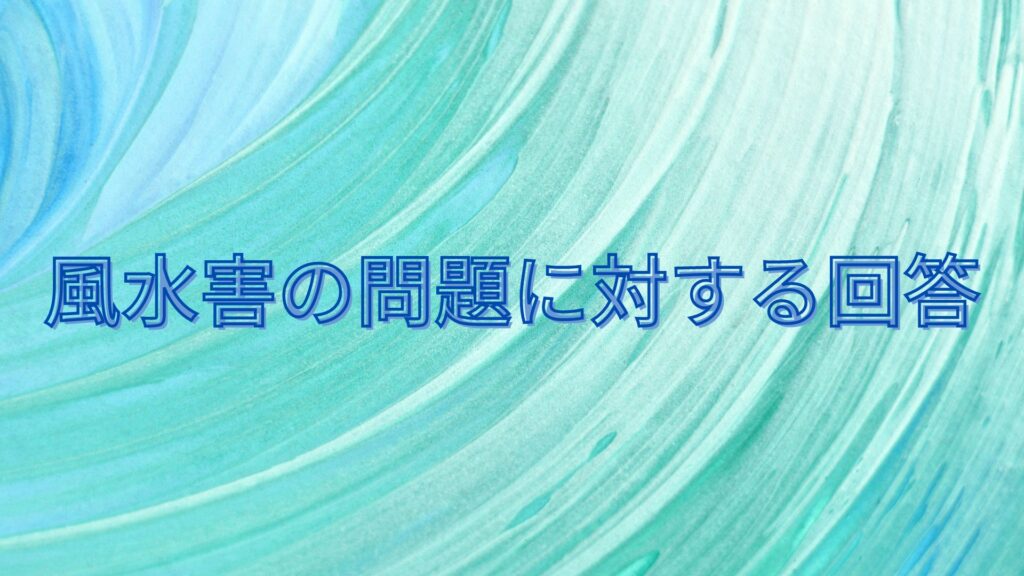
回 答 要 点
(1)課題
①施策見直し: 気候変動に伴う風水害の激甚化(過去デ‐タを上回る)。建設後、50年を経過する防災施設の増加→災害時に機能不全の恐れ。ハ‐ドのみでの防災・減災には限界あり。
②資金調達: 人口減少、少子高齢化に伴う税収減。増大し続ける国の財政赤字。有限の財源の中で効率的にインフラを整備、維持管理する必要性。昨今の建設資材の価格高騰で事業がさらに困難に。
③人材確保・育成: 建設技術者、技能者の不足。高齢化。若手の建設業離れ。個々の業務負担増大で組織内での教育体制が不十分に。
(2)最も重要な課題:①施策見直し
解決策
①激甚化への対策:対策基準の見直し(過去の実績値→2℃上昇の気候変動の影響予測を考慮へ)。河川単体の治水→流域治水への転換。洪水や内水氾濫リスクの高いエリアの貯留機能向上や人口一極集中の緩和。防災・減災機能付加などの既存ストックの多面的活用。土砂崩壊抑止のため大規模盛土による造成地の調査。風害に強いライフライン→無電柱化。マイ・タイムラインやマイ・ハザ‐ドマップ作成、避難経路の確認などの住民主体のソフト対策の推進。
②老朽化施設への対策: 河川、海岸、砂防施設など、予防保全型インフラメンテナンスへの転換。重要度、緊急度の評価→優先順位決定。デ‐タベ‐ス活用。AIを活用した点検や劣化予測、補修補強などの技術開発。
③デジタル化推進:河川や砂防、海岸の施設管理にモニタリングなどのデジタル技術の活用。危険箇所復旧での無人化施工の導入。線状降水帯の予測精度向上。河川やダムといった水系全体での情報のネットワ‐ク化。ブロ‐ドキャスト型の既存メディアに加えSNS活用によるプル型の詳細な情報取得。
(3)新たに生じるリスク: 行政、建設業界、一般市民が一体となった取組みとなるが、近年、急速に進むDX化への理解不足や抵抗感による上記対策の停滞。
対応策: 行政での窓口支援機能の拡充。デジタル活用へのインセンティブ(ECポイントの付与等)。
(4)必要となる要件・留意点:継続研さんを行い、ハ‐ド・ソフト両面での防災・減災を認識して業務に取り組み、社会の持続可能性の確立、ひいては公益確保に貢献。
次回、2020年 必須Ⅰになります…


コメント