今回は、前回の続きで、後半の解決するための具体的な実施方策を述べていきます。
Kayが自ら受験した技術士試験の復元回答をお示しします。



選択Ⅲ-2の問題文(再掲)
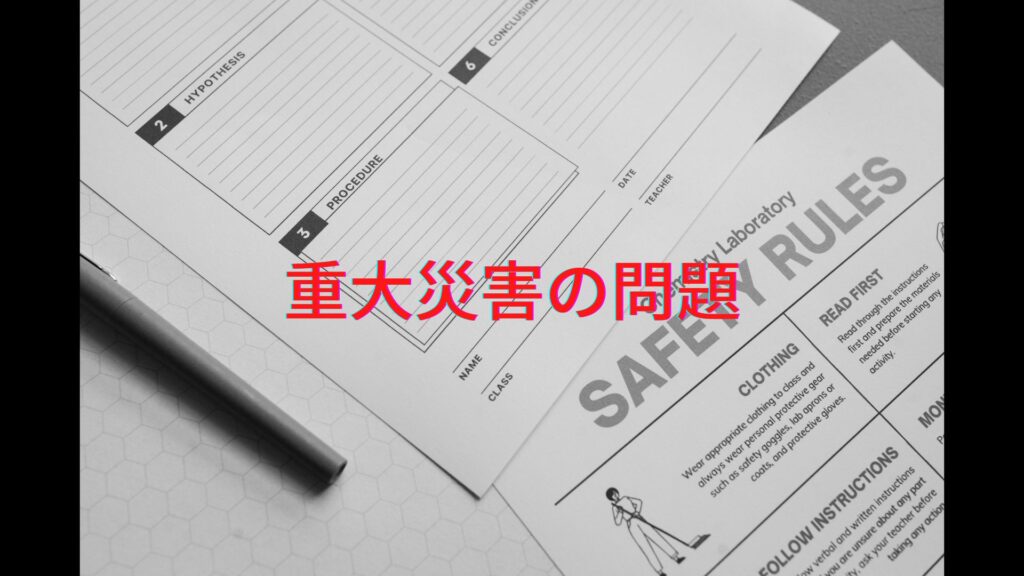
2013年 選択III‐2
建設業における労働災害の死亡者数は、1990年代前半には1000人前後で推移していたが、公共事業投資の大幅な抑制や現場の安全設備・安全管理の充実によって、ここ数年は300人台まで減少した。しかし、重大災害(一時に3人以上の労働者が業務上死傷またはり病した災害事故)は平成21年以降増加傾向にあり、社会的に問題となる事故も発生している。このような状況に対し、施工計画、施工設備及び積算の技術士として以下の問いに答えよ。
(1)建設産業や建設生産システムの現状を踏まえ、重大災害を誘発すると思われる要因を三つ挙げ、それぞれについて述べよ。
(2)(1)で挙げた三つの要因に対して、解決するための具体的な実施方策を論述せよ。
復元回答(後半)
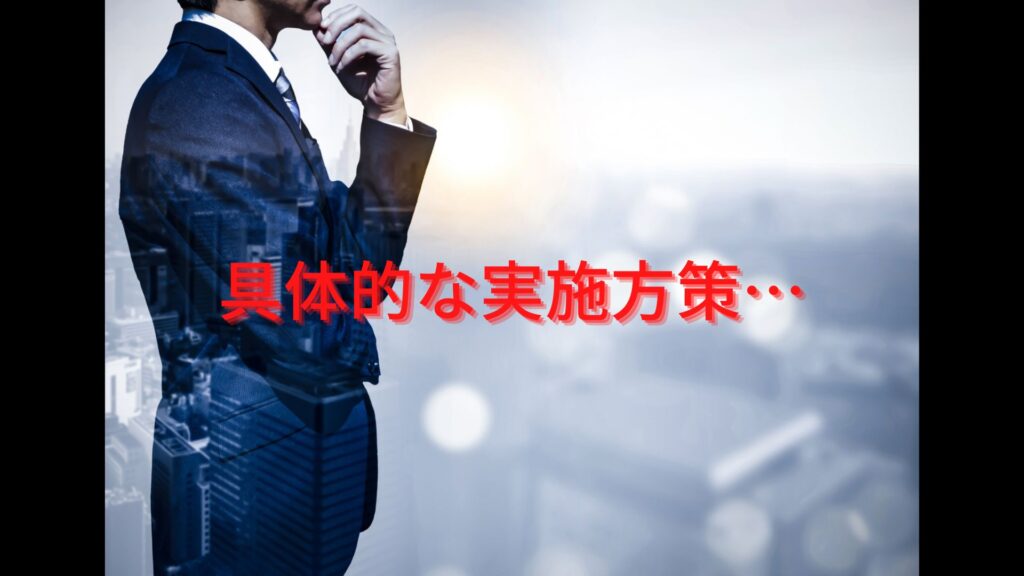
復 元 回 答
3.要因に対する解決のための具体的な実施方策
(1)建設事業環境の改善に向けた整備
a)着眼点:ダンピング防止や適性工期の確保、加えて若者入職促進、安全教育により、問題の根底から是正を図り、重大災害を抑止すべきと考える。
b)具体策:①オ‐プンブック方式により、協力業者への発注金額や安全対策費など、コスト構成の透明性を向上させ、金額根拠の薄い安値受注を防止する。②CMやPPPによる発注支援や、近隣や利害関係者に対するアカウンタビリティの強化により、発注前の諸問題の早期解決に努め適正工期を確保する。③官民協働で、建設業の魅力や社会への貢献度をPRする広報戦略を展開し、若者入職を促進する。④建設生産手法の変化を踏まえた安全教育を強化する。
(2)店社と現場のマネジメントサイクルの形成
a)着眼点:現場による日々の安全管理に、店社によるバックアップ機能を付加し、一連のマネジメントサイクルを形成すべきである。
b)具体策:①現場は、発生した労働災害やヒヤリハット事象を店社にフィ‐ドバックし、店社はこれらをデ‐タベ‐ス化し、RAのシナリオとして活用する。②店社による安全パトロ‐ルを定期的あるいは抜き打ちで実施し、不安全な作業や設備を是正する。③複数の人命に関わる非常事態時の現場体制や店社のバックアップ体制を明確に構築する。
(3)技術開発・活用促進と現場主義への転換
a)着眼点:技術開発・活用の推進や、監視を重視した現場主義への転換により、現場体質の改善を図り、重大災害の減少に寄与すべきである。
b)具体策:①NETIS登録や活用により、例えば、地山崩壊検知システムや有毒ガス探索ロボット、及び無人化施工などの技術開発や活用を促進する。②入札時の総合評価の評点対象として、NETIS登録技術の活用を掲げ、上記技術活用のインセンティブを高める。③受発注者間のコミュニケ‐ションを重視し、双務性の向上により、現場担当者の書類負担の軽減を図り、現場監視を重点化する。
4.おわりに
以上、実施方策を述べた。私は、技術の研鑽を継続し重大災害の抑止に貢献する所存である。以上
次回以降、直近4年の問題と回答要点になります…


コメント