- 必須Ⅰの頻出テーマは?
- 施工計画の選択Ⅲの頻出テーマは?
- 2題出題されるが、2題とも回答できそうならどう選べば良い?
Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の傾向を分析し、対応策を発信していきます。




必須Ⅰについて
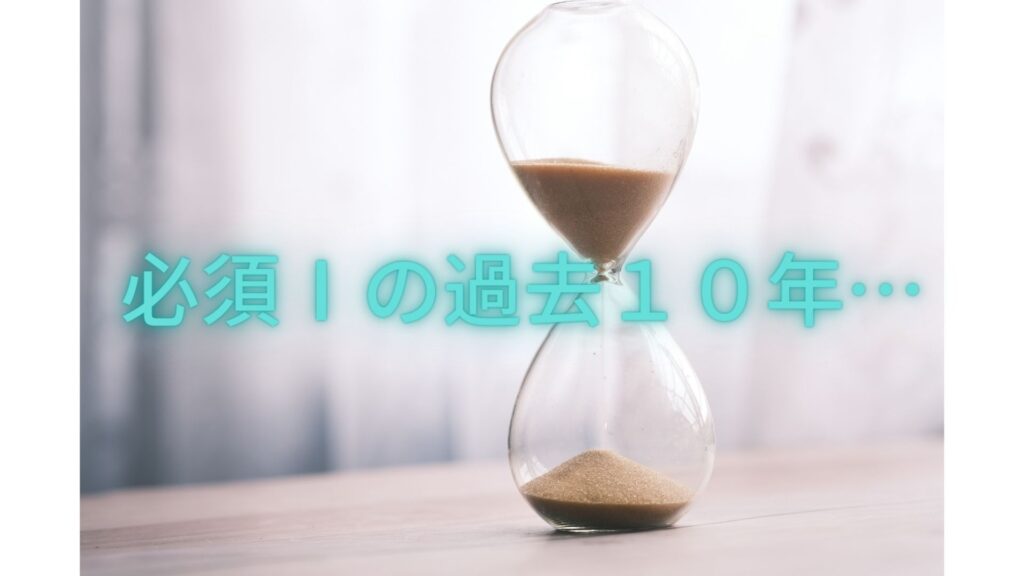
まず、必須Ⅰの過去の出題テーマと勝敗の分かれ目について、見解を申し上げます。
必須Ⅰは、ある程度、テ‐マを大別して骨子を整理し、課題、解決策、新たなリスクと対策を一覧表にすることでそれなりの対応が可能です。いくつかのテ‐マがロ‐テ‐ションして出題されている印象もあり、準備すべきテ‐マ数もそれほどではないと思われます。下の表1に、過去10年の出題テーマを一覧にまとめました。
表1:過去10年の必須Ⅰの出題テ‐マ

※太字は過去10年で複数回出題されたテ‐マ
※2013年~2018年の必須Ⅰは択一式のため掲載外
次に、表1をもとに、過去10年の頻出テーマを抽出したものを下表2としてまとめました。やはり建設部門の最大の使命ともいえる防災・減災が頻出テーマで、環境問題、維持管理などが続きます。
表2:必須Ⅰの過去10年の頻出テ‐マと出題回数

必須Ⅰの怖いところは、たった1問で判定されてしまうところです。最新の国の方向性や重要政策から大きく逸脱しないこと、題意と合致した課題・解決策で論理的な繋がりがあること、他の受験者と差別化する視点が要所にわずかでもあること、などがA評価の要件になると思われます。
選択Ⅲについて
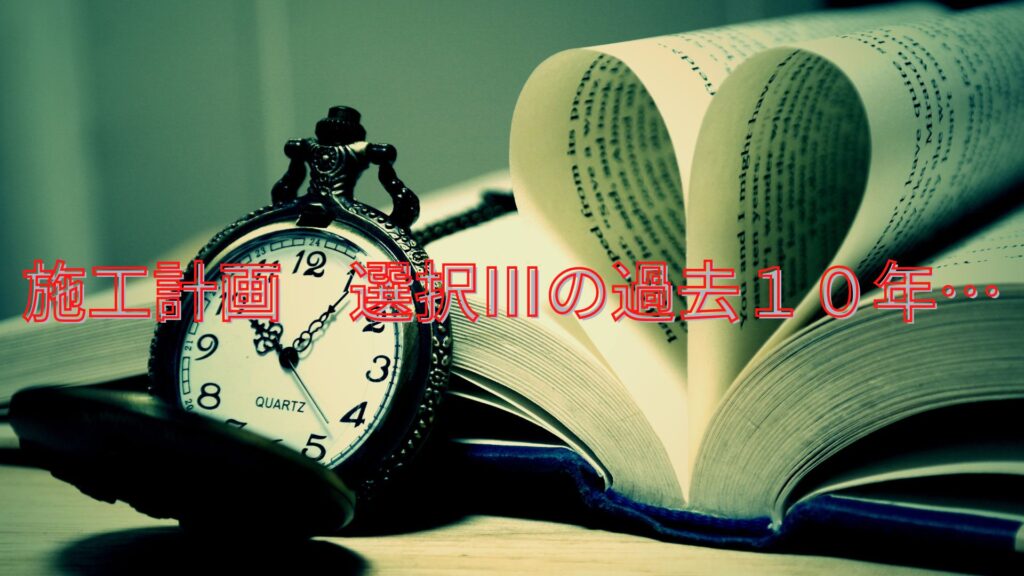
次に、選択Ⅲの過去の出題テーマと勝敗の分かれ目について、見解を申し上げます。
選択Ⅲは、必須Ⅰと同様で一覧表で整理しておけば、それなりに対応可能です。必須Ⅰよりも施工計画分野に特化し、より実務的な出題テ‐マも多いです。時として、必須Ⅰと違いがないような広いテ‐マも出題されます。仮に、必須Ⅰと同種のテ‐マが出題された場合は、課題解決の広さと深さで少々の違いが必要かもしれません。下の表3に、過去10年の出題テーマを一覧にまとめました。
表3:過去10年の選択Ⅲの出題テ‐マ

※太字は過去10年で複数回出題されたテ‐マ
次に、表3をもとに、過去10年の頻出テーマを抽出したものを下表4としてまとめました。こちらは、維持管理、品確法、生産性向上・担い手確保など、やはり施工計画に特化したテーマが頻出になります。
表4:選択Ⅲの過去10年の頻出テ‐マと出題回数

いずれも2題中1題を選ぶが…

必須Ⅰも選択Ⅲどちらも2問ずつ出題され、いずれかを選びます。
仮に、2問どちらも記述できそうであれば、周りの受験生が敬遠しそうな問題を選択するのがベタ‐です。皆が飛びつきそうな問題は、競争原理によってA評価レベルが引きあがってしまうからです。言うほど簡単なコトではないものの、このように本番で選べる状況になれば理想的ですね。少なくともどちらも手が出ない状況は回避できるように準備しておきたいところです。
まとめ
- 必須Ⅰでは、防災・減災、環境問題などが頻出テーマである
- 施工計画の選択Ⅲでは、維持管理や品確法、生産性向上・担い手確保などが良く出題されている
- 仮に、2問どちらも記述できそうであれば、周りの受験生が敬遠しそうな問題を選択するのがベタ‐
つづく…

コメント