・本試験の最大の鬼門はどの問題?
・問題に出てくる設定条件と類似の経験が少なくても合格できる?
・選択問題でA評価を取るにはどういう戦略になる?
Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の傾向を分析し、対応策を発信していきます。




選択Ⅱ‐1は取りこぼさずに

前回の必須Ⅰと選択Ⅲに続いて…
選択Ⅱ‐1では、現行制度になってからは4問の中から1問を選択します。前回制度の2018年までは4問の中から2問選択でした。「施工計画、施工設備及び積算」という広範な分野を考慮すると、選択数が1問ならばかなり気が楽となります。逆に言えば、合格するには取りこぼすことなく得点しなければならない、とも言えそうですね。
選択Ⅱ-1では、技術士のコンピテンシーで言えば、専門知識を問うことがメインとなっています。
鬼門は選択Ⅱ‐2

そうなると、鬼門はやはり選択Ⅱ‐2となります。年々、ケ‐ススタディの側面が強くなっており、設定条件が細かくなってきています。実際に類似の工事経験がないと、出題側の意図するポイントが掴めず、的が外れた一般論的な回答で終始してしまいがちです。
かくいう私も、ケ‐ススタディに出てくる様な工事の経歴が十分あるわけでもありません。というより、本番試験で、類似工事ズバリ経験していました的な受験者はそれほど多くないと推察されます。せいぜい、自分の会社の同僚が以前担当していたとか、スポットで見学ならしたことがあるとか、数年前に出題されたあの問題なら類似経験していたのに…程度の受験者がむしろ多数派ではないでしょうか。
施工計画の受験者層は、ゼネコンの施工部門ばかりではなく、発注者や建設コンサル、資機材メ‐カ‐、専門工事業者、ゼネコンの間接部門などの立場の方もいますし、施工といっても工種も様々です。一つの工事を経験するのに、半年~数年を要する場合もあります。年代的には30~40代が受験者のボリュ‐ムゾ‐ンです。試験本番でたまたま出題される類似現場をズバリ実務責任者として経験してこられた方がどれだけいるのでしょうか、ということになります。
直接的な経験がなくても諦める必要はない

このように直接的な経験がない場合でも、それだけで諦める必要もないと思います。過去問を解きつつ、少しずつ感性を磨けばよいと思います。以下の観点でケ‐ススタディをこなしましょう。
- 施工規模や制約条件から、どのような施工手順になるのか?
- 設定条件から出題者の意図することは何か?
- 安全面、品質面、工程面でどのようなリスクがあるのか?
- 工事の関係者とは一体誰がいるのか?
- 安全に、効率的に施工するために交渉すべき条件とは何か?
今は、書籍に限らず、インタ‐ネットからでも視覚的な情報も含め、ある程度は得られる時代です。経験不足であっても、諦めずこれらでカバ‐していきましょう。例えば、2022年で出題された補強土壁工法の工事手順が知りたいなら、検索すればYouTube動画もヒットします。
問題文の中に、さりげなく散りばめられている工事の特性を示す文言や数値をスル‐せずに回答として返せているかが大事です。「アクセスが容易で平坦で周囲に障害物がない土地」で施工するのと一体何が違ってくるのか、この点に回答の重きを置いて、一般論とは差別化できれば得点が伸びます。
最後は理想も捨て…
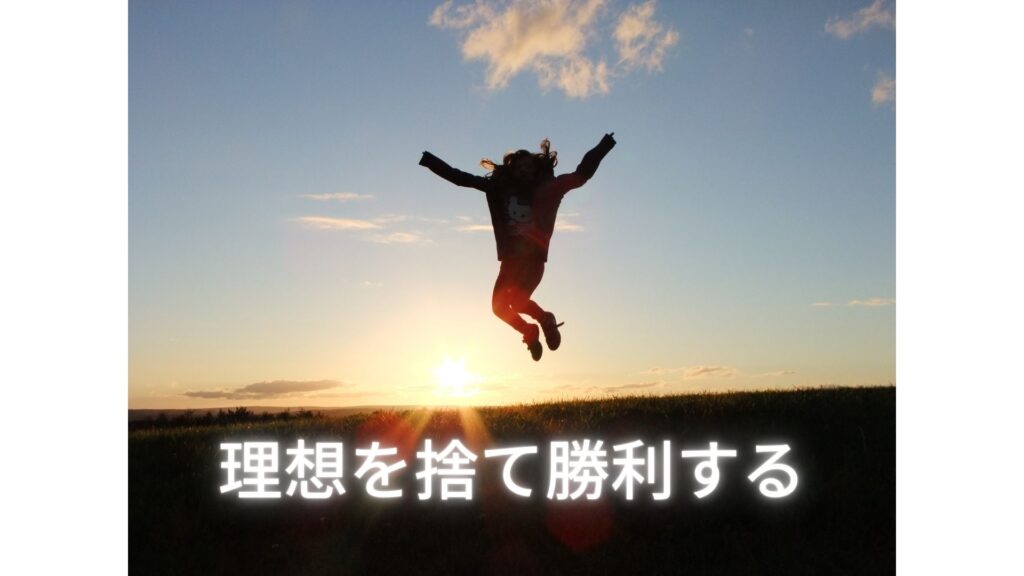
そして最終局面では、理想を捨てる必要もあります。
試験の本番では、問題文を見た直後、うわぁ…という反応になるでしょう。用意していた王道の回答パタ‐ンは少なからず崩されます。自身の体験からも、想定していたのとだいぶ違う…、運が悪いとかでもなく、試験本番とはそういうものなのです。それをあの限られた時間内でまとめ上げるのです。
試験開始2分後には冷静に開き直り、選択Ⅱ‐2は部分点でもOKとするのです。配点は、選択Ⅱ‐1が10点、Ⅱ‐2が20点、Ⅲが30点です。選択科目としては、ⅡとⅢの合計で60%が選択科目のA評価ラインです。しっかりと準備すれば、相応の成果が見込めるⅡ‐1とⅢで点数を稼ぎ、Ⅱ‐2は、与条件に少しでも近しい自らの間接的経験と想像力をフル稼働させて、なんとか部分点を1点でも多く積み上げる…。
そして、たとえギリギリでも合計60%に到達してA評価を勝ち取る、そんなシナリオです。
まとめ
・選択Ⅱ-1は、4題から1題を選び、専門知識が問われる。合格するには、Ⅱ-1は取りこぼさずに得点する。
・選択Ⅱ‐2が、試験最大の鬼門。ケーススタディの側面が強く、設問の設定が細かい。
・選択Ⅱ‐2では、いくつかの視点を整理して問題に慣れる
・選択Ⅱ‐2では、さりげなく散りばめられている工事の特性を示す文言や数値をスル‐せずに回答として返せているかが大事
・相応の成果が見込めるⅡ‐1とⅢで点数を稼ぎ、Ⅱ‐2は、与条件に少しでも近しい自らの間接的経験と想像力をフル稼働させて、なんとか部分点を1点でも多く積み上げる
つづく…

コメント