- 技術士二次試験の合格基準とは?
- 失意のどん底から這い上がったときに得た気付きとは?
- 2回目の対策はどのように始めた?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士を目指して合格に至った経緯を体験をもとに綴っていきます。



本試験の成績
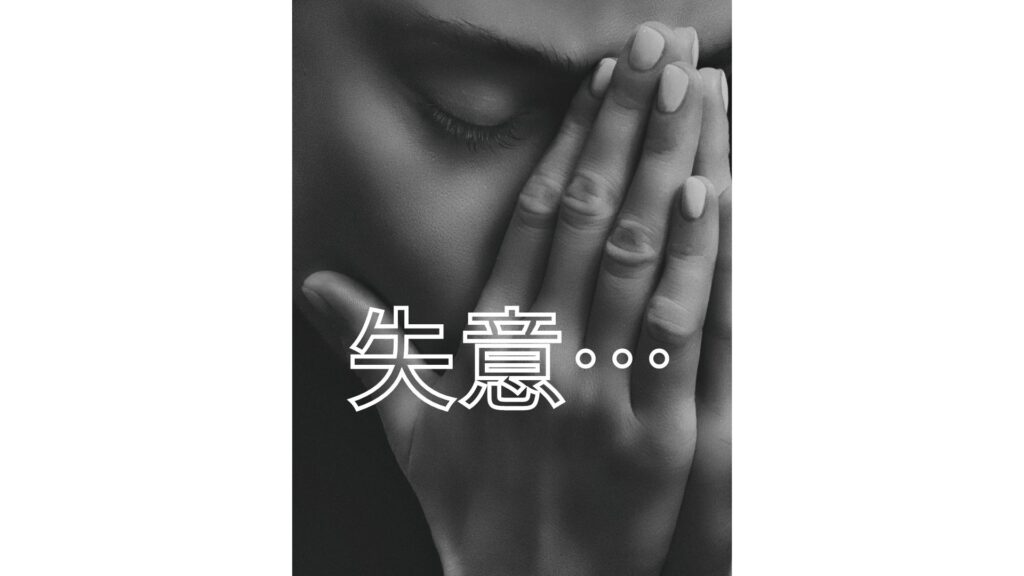
合格発表から数日後、成績表が送付されてきました。内容は、以下の通りでした。
必須科目:A
選択科目:B
不合格
Aは60%以上の得点であり、Bは40~60%の得点という意味です。40%未満であればC評価となります。両方の科目ともにA評価で筆記試験合格となります。選択科目は2問の平均点で評価されます。
失意のどん底から這い上がり…
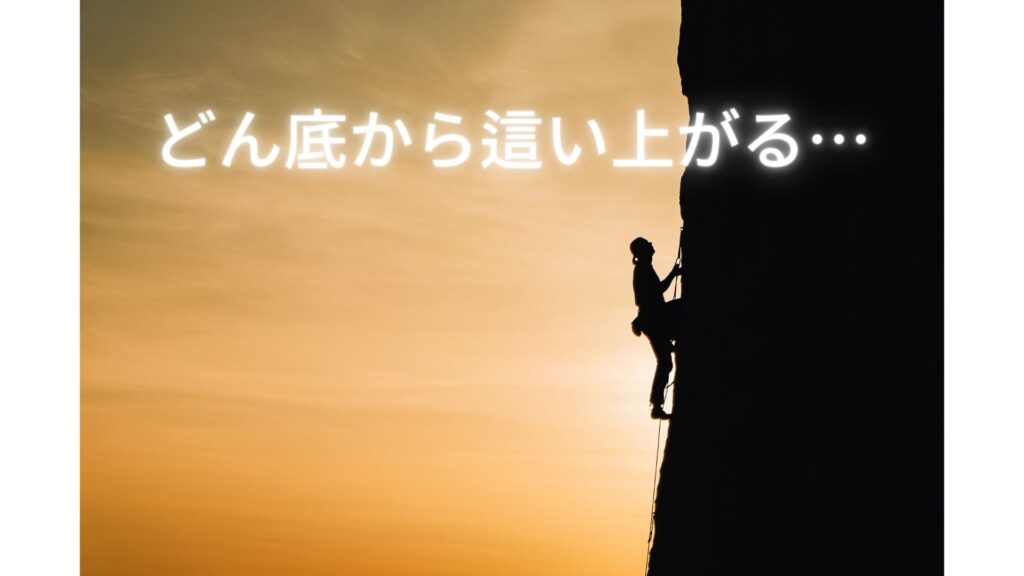
当時、この成績を見て、かろうじて救われた感覚になってきました。
 Kay
Kay片方A評価であったなら、まだ良かった
…と。箸にも棒にもかからなかったわけでもないのだからと。
たしかに、再起するために希望がエネルギ‐となる、という意味ではアリかもしれません。ですが、厳しさを正しく知る意味では、両方B評価の方がむしろ良かったのかもしれません。今思うと、次年度の試験でアダになった様にも思うからです。とはいえ、この試験の本番の恐ろしさを思い知ることはできました。自分の知識は、まだまだ穴だらけであったと。
また、自分の復元論文を既技術士の方々に見てもらう様にしました。友人のル‐トで知り合った方にもお願いしました。その方は、ボランティアで論文添削をされていました。指摘を受ける中で、論点のずれを理解できてきました。設問を見て、1800字でフル回答する練習ばかりしていましたが、出題者の意図を踏まえた骨子になっているか、論理的な繋がりがあるかの視点に気づき始めてきました。
その年内は、不合格になった原因分析とこうした情報収集をし、年明けから再挑戦していくことにしました。合格発表後の2、3週間は、失意のあまり再受験のイメ‐ジすら湧かなかったのですが、そのどん底からは何とか這い上がることになりました。
2度目の挑戦を開始
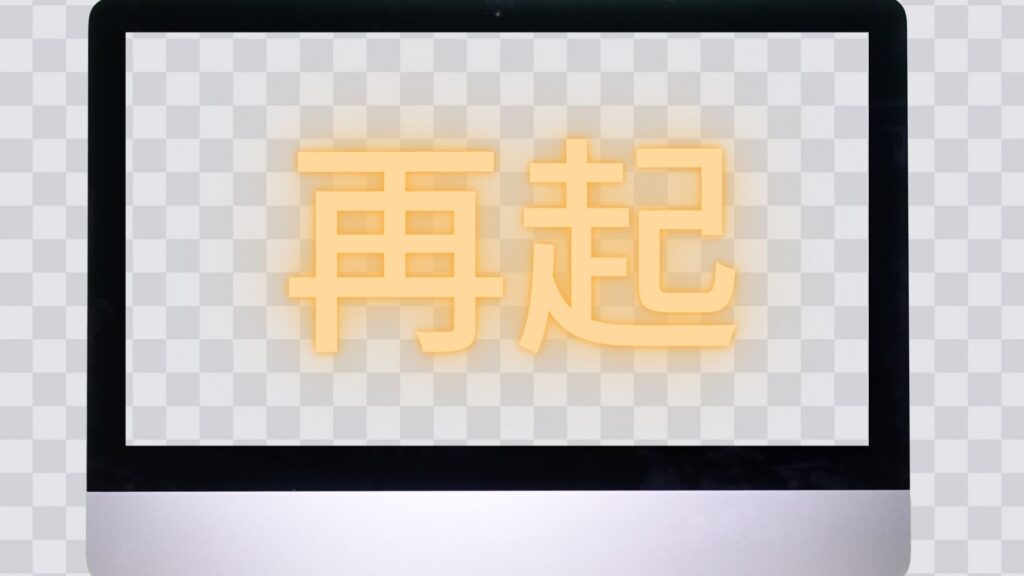
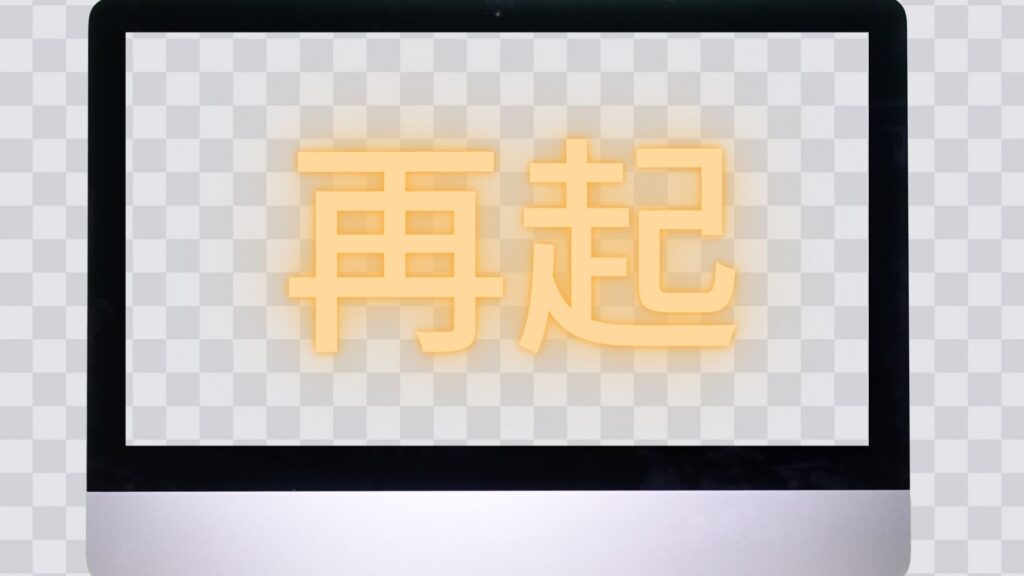
2012年となり、2回目の受験対策を開始しました。
昨年とは別のスク‐ルに通うことにしました。この年は、大人数で行うスク‐リングよりも、少人数制と論文添削を重視して決めました。全体のスク‐リングで得られる知識には限界もあり、同じスク‐ルでは昨年とほぼ同じ情報を聞くだけになるだろうと考えました。
何としても今年で合格する。来年には試験制度改正の話が出ていたので、さらに拍車がかかりました。昨年B評価だった選択科目の強化を重点的に行いました。専門書を数冊買いこんで、弱点を潰していきました。


15問の出題から選択の幅を増やすために安全管理分野の勉強もしました。
このスク‐ルではT先生にご指導いただきました。文書のまとめ方にこだわりがあり、独自の論法を確立されておりました。読む側としても、確かに分かりやすい文面だなと思いました。この論法自体は、翌年の合格年度にも継承されました。
まとめ
- 試験の成績は奇跡的に片方A、これが再起のエネルギーに。そのことが後々のアダにも…。
- 出題者の意図の把握&論理的なつながりが論文には必要です。
- 2回目はより少人数制のスクールを選択。文書のまとめ方を学びました。
次回は…




コメント