- 1年以上前に発生したあの出来事が、なぜ今年の必須論文テーマに?
- 前年以上の手応えを感じて臨んだ合格発表の結果は?
- 試験成績は自分の出来云々だけに左右されるとは限らない?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士を目指して合格に至った経緯を体験をもとに綴っていきます。



2度目の本試験
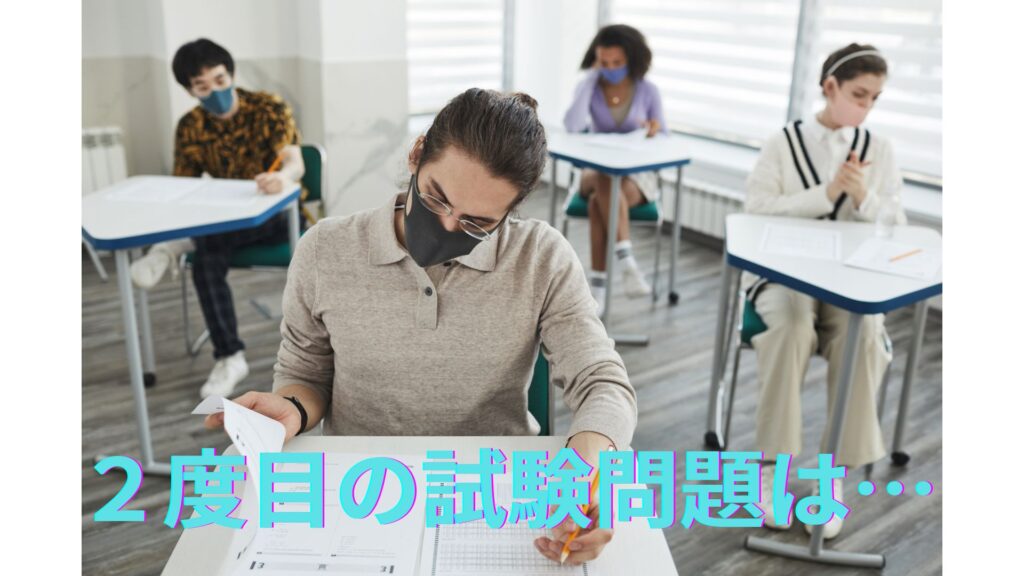
午前の必須科目では、東日本大震災のテ‐マが出題されました。前年の3月に発生し、その年の試験ではなく、ひと呼吸置いてから満を持して出てきました。おそらく前年の時点では、国の方向性や政策も明確に定まりきれていなかったから出題が見送られたと推察されます。当然、予測できていたテ‐マでしたので、ほぼ準備していた骨子で対応しました。
午後の選択科目は、ユニットプライス型積算方式と実行予算の2題をチョイスしました。いずれも変化球はあったもののテ‐マ自体は想定の範囲内ではありました。終了した時点では、不安はなくもないが、少なくとも前年よりは出来たという感触を得て、試験を終えることができました。
そして合格発表…
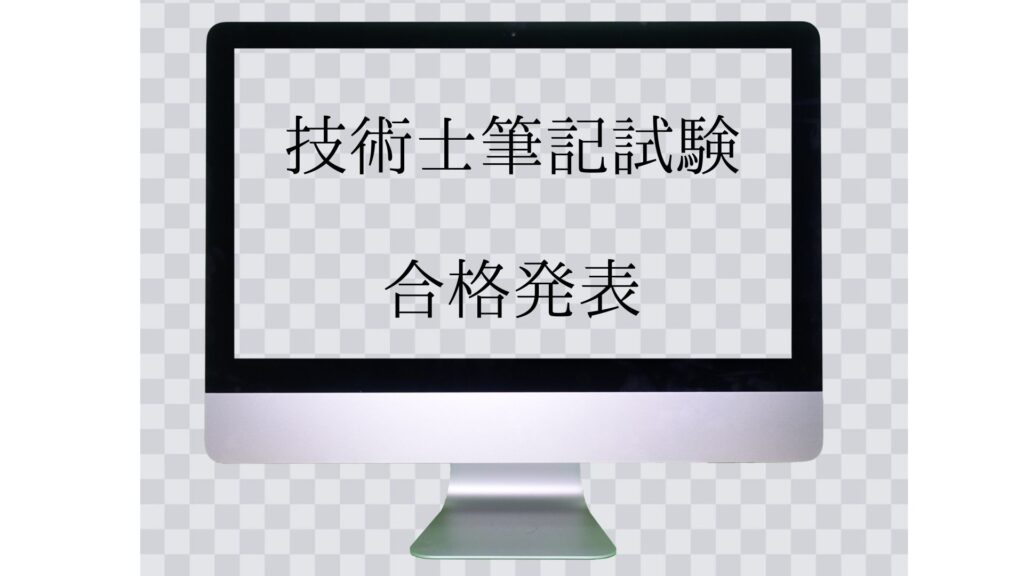
さらに時は流れ、再び合格発表日の朝を迎えました。
昨年よりは落ち着いた心境で、この合格発表に臨みました。とはいえ、やはり少し早めに目が覚め、しばらくパソコンの前で例の某掲示板のコメントを眺めていました。
そして、発表…!
(番号検索中…)
はっ…!
 Kay
Kayまたも…またしても、自分の番号はなかった…
試験直後に復元論文をT先生に見てもらい、おそらく合格だろうとまで言っていただいていたのに…。昨年よりは、結果に対して冷静でいられたけれど、なぜ駄目だったのか、疑問はむしろ大きかったのです。選択科目の実行予算の回答に欠陥があったのか…?
想定外すぎて驚いた試験成績
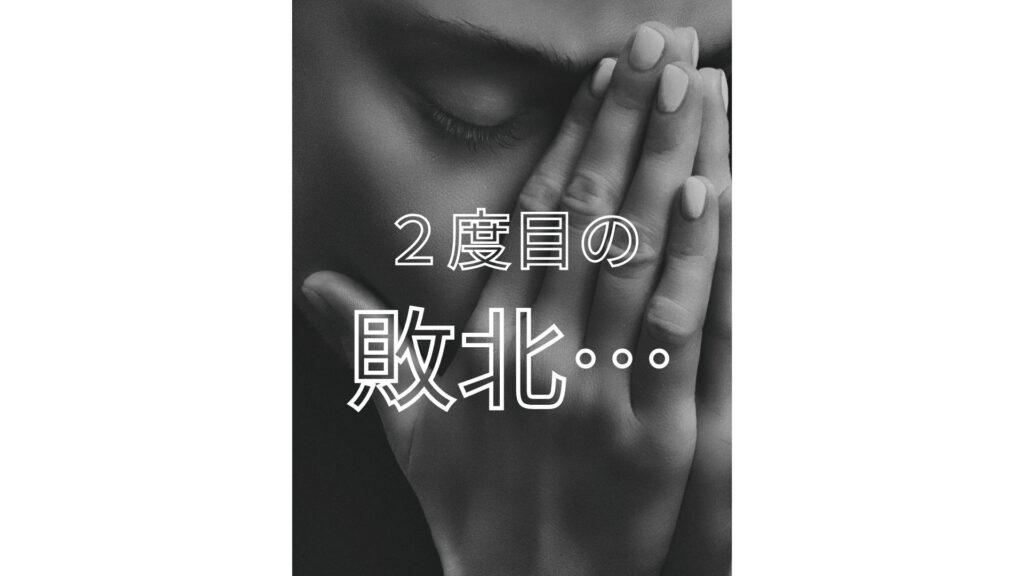
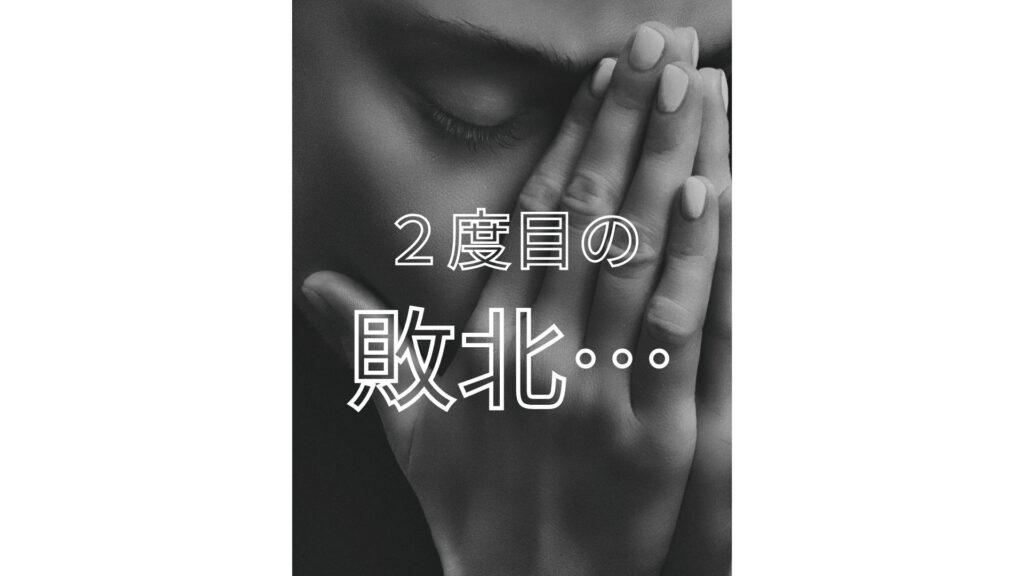
数日後、送られてきた成績表を確認しました。
必須科目:B
選択科目:A
不合格
なんと、準備して予想に近いテ‐マが出た必須がB評価!昨年とも評価が入れ替わった格好です。ただ、今の私が冷静に当時の復元論文を見返すと、課題の抽出までは大きな減点はないと思いますが、解決策に偏りがあったなと思います。しかも、テ‐マとして予想できる問題なだけに、多くの受験生にとっても準備万端であり、A評価レベルはより高いものに昇華していったと推察されます。
こうして、またも厳しい現実を突きつけられ…。
政権交代となり、アベノミクスで株価の急騰が取りざたされたあの頃…、
試験方式は大幅な改正へと突入していくのでした…。
まとめ
- 震災をテーマにした論文が1年、間を空けての出題。国の方向性や政策が出たタイミングだったからと推察。
- 前年よりも手応えはあったが2度目の不合格…。
- 必須がまさかのB評価…。自分の出来だけではなく、受験生全体の出来にも影響を受けるかも。
次回は…




コメント