- 試験制度が大幅改正。戦慄を憶えた改正の内容とは?
- 今までの知識だけでは全く戦えない。打開策は?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士を目指して合格に至った経緯を体験をもとに綴っていきます。



試験制度改正の戦慄

2013年度の試験大綱が発表され、ベ‐ルに包まれていた改正の試験方式がぼんやりと見えてきました。必須科目は、3枚論文を廃止して15問の択一式へ。選択科目は、専門知識を問う問題が2題、専門的応用能力を問う問題が1題、課題解決能力を問う問題が1題、という具合でした。また、それぞれに選択できる問題数は倍くらいになる、様なことが公表されていました。
この発表を知って、戦慄を憶えました。当時の己の戦慄を文書化すると以下の感じです。
 Kay
Kay必須科目が択一式になるのは、まあよい。しっかり勉強すればむしろ昨年みたいな落ち方はしなくなるだろう。
ヤバいのは選択科目の方だ。選択できる問題数が激減していく。自分は入札契約分野が中心だったが、新方式の試験ではおそらくそれでは全く通用しないだろう…。
従来方式での選択科目は、15題出題され2題を選べるので、自分の得意分野に絞って対策することが可能でした。しかし、この改正によって、「そのような偏った知識のみの者には合格させない」という意図がはっきりと窺えました。この考え方自体は、現行方式でも踏襲されています。
この「施工計画、施工設備及び積算」という科目、やはりメインは積算ではなく施工計画です。出題数を大幅に絞り込むなら、自分にとって不利な構成になるのは目に見えていました。したがって、自分には2つの選択肢のいずれか一つを選ぶしかないことに気づきました。
- 技術士になるのを諦める
- 施工の分野もイチから勉強する
最初から❷を選んだというより、❶はないよねの消去法によって、結果的に❷が残りました。要するには、諦められないけれど、勝てる目途が立たない、という状態です。前年の同時期のほうが、はるかに合格の可能性を感じられていました。この状況を変えるなら、今までと抜本的にやり方を変えるしかないと考え…。



投資だ。もっと金銭を投下してでも今の自分にない知識を得ていくしかない。
これが結論でした。そうして、施工計画の科目に特化したマンツ‐マン講義で、添削無制限のスク‐ルを選びました。受講料は今までで最も高額でしたが、試験制度改正が判断を後押しした格好でした。そして、この判断は間違いではなかったことを証明していくことになります。
覚悟を決めての3度目
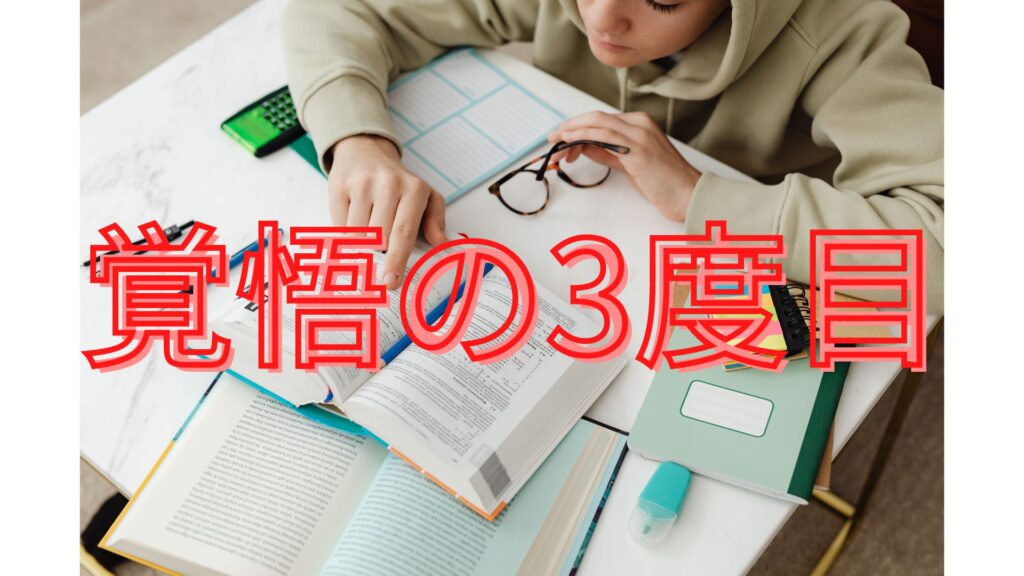
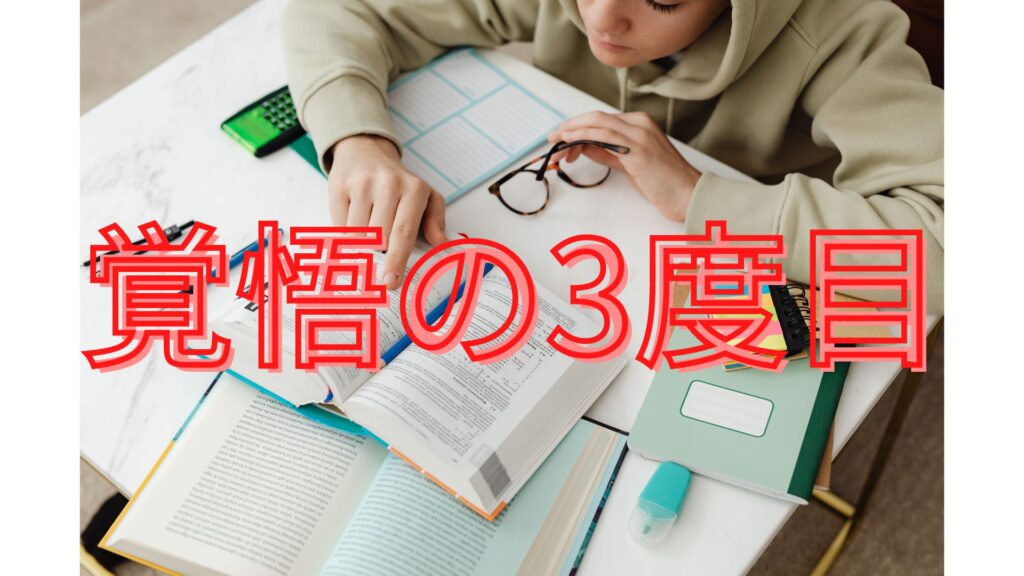
このスク‐ルでは、K先生が私の担当講師でした。ゼネコンの施工部門出身の方で、上流の国土交通政策から実際の業務実態まで、幅広く深い知識をお持ちでした。昨年の復元論文をお見せしたところ、数多くの指摘がなされました。この2年で、必須と選択、一度ずつA評価を取った実績など、一旦リセットした方が良いなと直感で感じました。とにかく、K先生の指摘をよく聞いて、イチから積み上げをしなおす覚悟で臨みました。
冒頭で記述しても良かったのですが、
まずは、そこから指導を受けました。2年間、温めてきた私の3000字版の体験論文は根本的に見直しとなりました。問題認識や解決、効果ともに内容が薄いとの判断です。K先生との試行錯誤のやりとりを経て、4月の上旬には、ほぼ完成に至りました。
まとめ
- 試験制度の大幅改正によって、自分の得意とする分野を選択できる確率が激減する見通しに…
- 現状の知識では絶対量が不足しているなら、しかるべき投資も必要
次回は…




コメント