- 試験制度の大幅改正の中、苦手分野にどういう対策をしてきた?
- 今までの受験経験で得た、あまり語られることのない経験論とは?
- 試験制度改正後、初の筆記試験。その内容は?感触は?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士を目指して合格に至った経緯を体験をもとに綴っていきます。



もっとも充実した時期
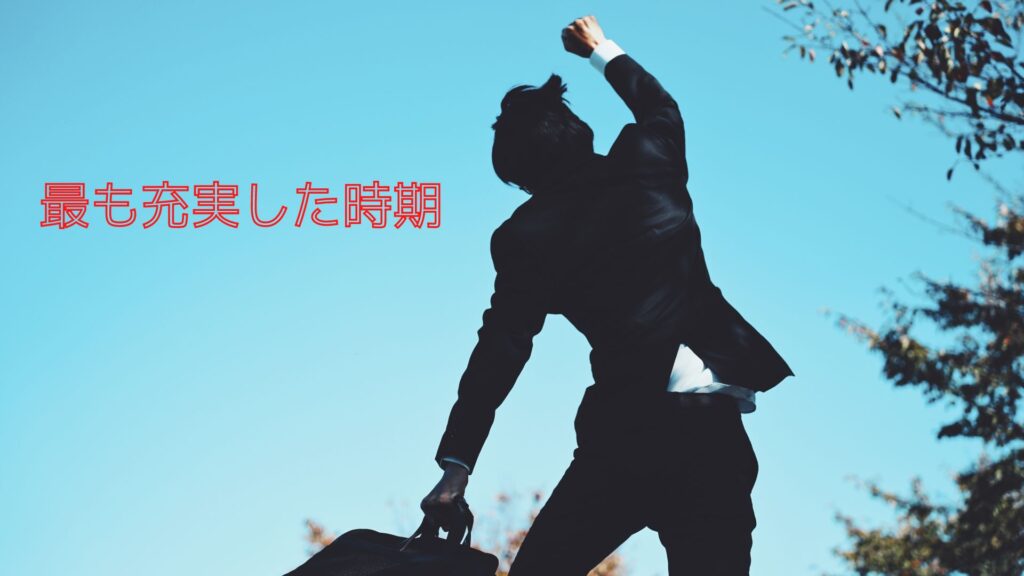
選択論文も添削を依頼すれば、ことごとく不合格判定で要再提出の嵐となりました。3回、4回の論文の練り直しはザラで、最大7回練り直したテ‐マもありました。今までの先生であれば、だいたい2回、せいぜい3回目ともなれば合格点となっていました。自分の専門知識の広さ、深さともに欠けていたのを改めて実感する日々でした。今思えば、技術士になる過程でもっとも充実した時期だったかと思います。
これまでの2年間に比べれば、勉強の時間効率も向上していました。主に、休日を勉強に充てていましたが、極端に寝る時間を削るまではしなくなりました。初年度は、試行錯誤が多く、結果的に遠回りで無駄となる時間も多かったです。その意味でも、本ブログが少しでもショ‐トカットの情報となれたら幸いです。
講師が色々なら試験官だって…

本番直前に行われる模擬試験は、毎年受講しているスク‐ルで受けてきましたが、この年は2つのスク‐ルで受験しました。やはりスク‐ルや講師によって、それぞれ特色があると考えていたからです。だいたい、模試1回で4~5万円でしたが、これも自己投資と捉えました。
本番の試験の採点でも、試験官2名が別々に採点し平均点を採用するという話があります。これは、試験官の主観による評価点の偏りをなくすためだと言われています。
 Kay
Kay講師が色々なら試験官だって色々…
…という事が結論ではないでしょうか。ならば、
同じ講師に何回も添削を受けるうちに点数は高くなりますが、他の講師に見せた途端、指摘のオンパレ‐ド・・。これは経験者であれば、あるある現象ではないでしょうか。
一人の同じ講師から80点を取るよりも、3人の講師全員から確実に60点以上を取る方が難しいかもしれません。
もちろん、個々の先生方を不信に感じているのではありません。これは、3年間の受験経験を経て悟るように分かってきたことです。当然、論文試験であっても、ある程度の正解や得点となるポイントは設定されているでしょう。ですが、択一の様に、誰が見ても明らかな一つだけの正解を当てる試験とは本質的に異なるのです。
改正後、初の筆記試験
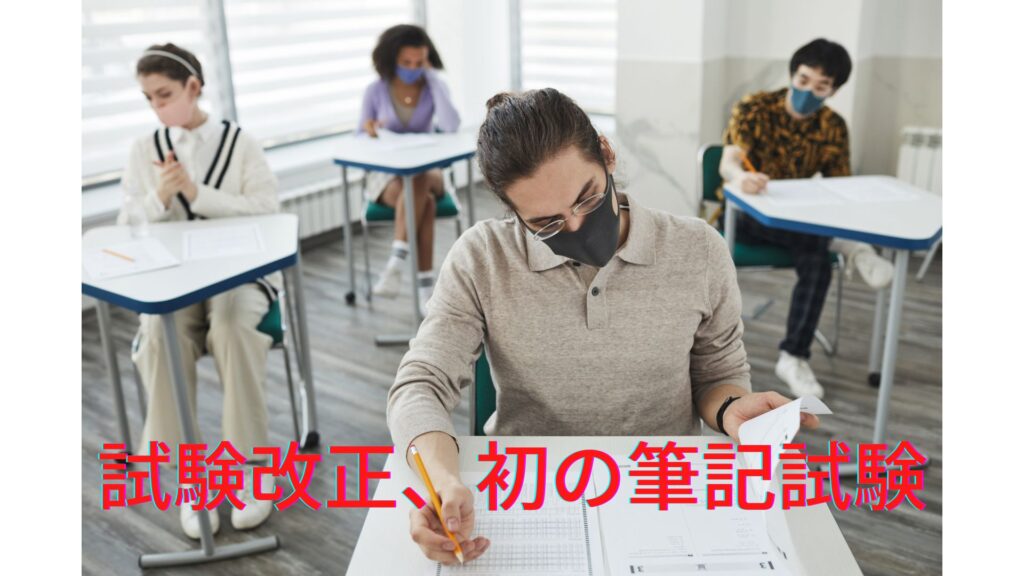
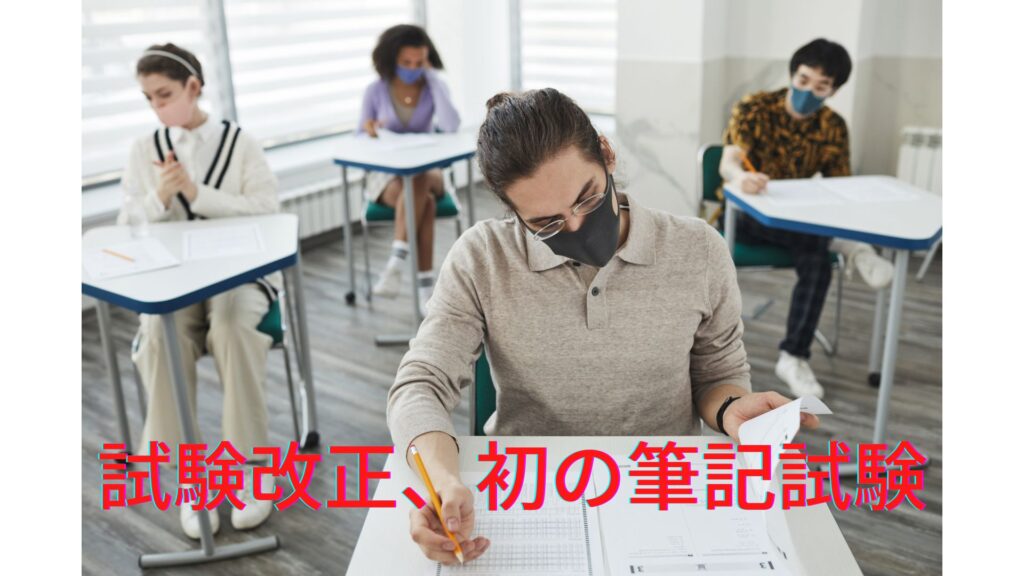
こうして時が流れ、自身3度目となる二次筆記試験日を迎えました。
印象としては、初年度での手探りの意味もあってか、対応しやすい問題が多かった様に思えました。確実に正解と言える設問がちょうど9個くらいあったので、まあ大丈夫だろうと思いました。(現行制度では択一式は廃止)
次は、選択科目です。まずは、専門知識及び応用能力の試験です。以下の内容を制限時間2時間でまとめなければならず、時間勝負の側面も大きいです。
続いて、選択科目の課題解決能力を問う試験です。こちらも制限時間2時間なので、多少ゆとりはあります。
試験直後の感想としては、コンクリ‐ト、工程管理、安全管理、そして入札・契約と、施工計画の科目の中から満遍なく出題されたのは、予想通りでした。この半年余りで、それまで対応できなかった分野をイチから準備してきましたが、それでも自分にとってキツイ本番となりました。
まとめ
- 施工の知識・経験が豊富な先生の厳しい添削指導のもとで、地道な専門知識の積み上げ。
- 『講師も色々なら試験官だって色々』が結論では。目指すべきは誰が見ても60点以上の論文。
- 改正後初の試験は、問題選択の幅が狭まり、幅広い知識・経験を要する厳しい試験に…
次回は…




コメント