- 私の過去のデジタル技術の変遷は?
- 現在のDXの取り組み内容は?
- DX推進計画、内容や潜在するリスクは?
Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の問題に斬り込み、回答要点を発信していきます。




総監/記述式/2022年/回答要点
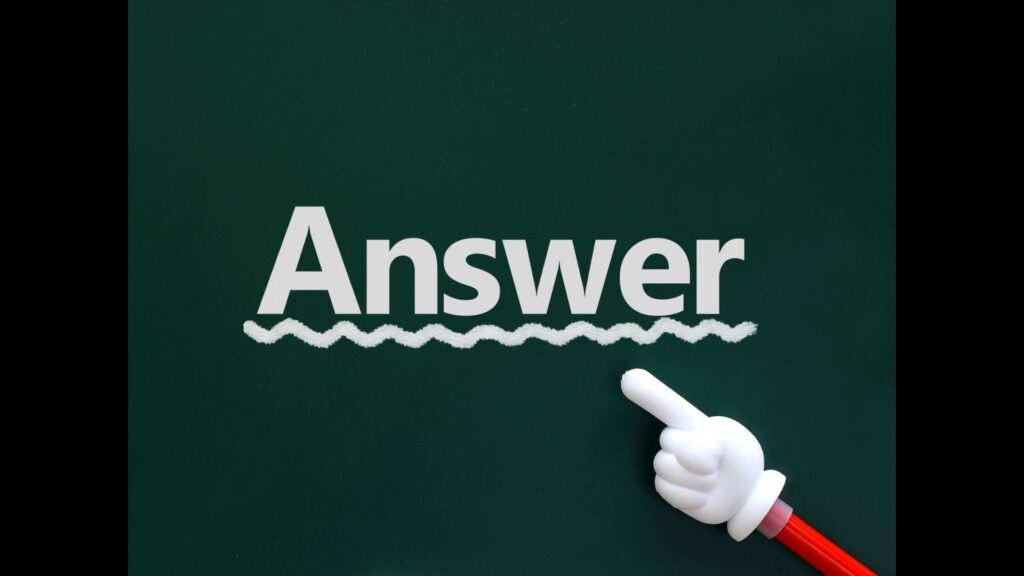
(1)私が取り上げる事業や組織の内容とデジタル技術の利用状況
①事業や組織の概要及び役割、私の立場: 集合住宅建設事業。社員400人の総合建設業。私の立場は、積算部の責任者で各プロジェクト全体を見渡す役割がある。
②経営資源、アウトプット、業務プロセス: 設計30人、積算10人、施工80人。業務用にPCとタブレット端末を使用。技術士(建設部門)、一級建築士、一級建築施工管理技士などの資格者が一定数在籍。鉄筋コンクリート造の集合住宅を建設しオーナーに引き渡す。入居確保のための提案やサポートも行う。設計施工一括方式での請負。基本設計⇒概算⇒基本合意⇒詳細設計⇒詳細見積⇒契約締結⇒施工⇒竣工引き渡し、のプロセスとなる。
③過去のデジタル技術の利用の変遷
・設定した期間の初期段階でのデジタル技術の利用状況:本項では、BIMモデルを挙げる。初期段階では、3D化した建築モデルを顧客とイメージ共有し合意形成に活用。
・現在のデジタル技術の利用状況とこれまでの変遷:初期段階から5年程度経過⇒構成する部材の属性情報を付与しファブと情報共有⇒部材のプレキャスト化、ユニット化に寄与。
・変遷の過程で得られた効用と副作用
効用
・現場作業の軽減や単純化で工程短縮(経済性管理)
・現場での産廃やCO2発生の抑制(社会環境管理)
副作用
・直接的コストは上昇⇒工期短縮に伴い仮設維持費や現場職員の人件費などの間接的コストは縮減⇒両者を相殺(経済性管理)
・部材が重量化⇒楊重する機械も大型化⇒転倒による重大災害の発生が二次リスク(安全管理)
(2) DXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組
①取組の概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容
・手書きノートアプリケーション⇒社内スタッフにタブレット端末と専用ペンを支給⇒タブレット上の図面・文書データに直接書き込み⇒他者と書き込みデータの共有も可能
・Web会議で設計や施工の方針を共有する場合などで特に有効。視覚的に思考プロセスを参加者と共有しやすい。顧客や協力業者も巻き込むとさらに効果大。
②もたらされる利点と問題点
利点
・ペーパーレス化が進み、機密情報の焼却処分が不要になった(社会環境管理)。
・用紙、コピー機、処分費などの社内固定費の削減(経済性管理)
・共有データで検討⇒部門間の不一致や行き違いによるミス抑制(経済性管理)
問題点
・一つの図面データファイルを複数人で共有⇒個々が自己都合でデータファイルを移動または保管すると管理不能⇒保管場所や使用ルールの設定必要(情報管理)
(3)DX推進計画及びタスクフォース
①中核となるメンバー
・設計部門長:建築意匠・構造・設備設計を統括。経歴30年。
・積算部門長:私。建築積算業務の統括。経歴20年。
・工事部門長:工事部門の統括。経歴25年。
・技術本部長:設計、積算、工事の技術系を統括。経歴35年。
・DX推進部門長:社内のネットワーク管理、DXによる改善活動。経歴20年。
・社外IT系コンサルタント: AI技術活用の支援、助言。経歴20年。
②計画策定に必要な工程と各工程の説明
第1~2週:DX推進計画のタスクフォースの目的の共有。経営トップより説明
第3~4週:各部門から現状の業務の問題点の抽出
第5~6週:問題点の取捨選択および複合化、優先順位の決定
第7~8週:実現目標の設定
第9~10週:実現目標に向けた具体的な取組内容の想定
第11~12週:取組内容に係るリソース(費用、期間、作業人員等)の見積と、実現に伴う経済的な成果の検証。
第13週:経営トップとの情報共有とプロジェクト実行可否の最終意思決定。
③私が最も重要と考える工程と理由
第11~12週:取組内容に係るリソース(費用、期間、作業人員等)の見積と、実現に伴う経済的な成果の検証。
理由:フィージビリティスタディの工程に該当(経済性管理)。投入するリソースに見合う経済的成果の有無の検証がなければ、DX推進の妥当性自体が不明なままとなる。
④実現目標と取組内容、最も重大な障害とその克服策
実現目標: AIによるBIMモデル自動生成。従来の2次元の図面データをAIが自動解析をし、BIMモデルに変換。
取組内容: 現状、人海戦術で行っている作業を分析し、AIにてディープラーニングさせ自動化させる。
最も重大な障害:二次リスクとして、AIによって生成されたBIMデータを技術者が過信し、自力で妥当性を検証する技量が低下
克服策
・対策として検証の手順書の策定(情報管理)
・上記の手順書を基に若手の指導(人的資源管理)
次回、2021年の問題を見ていきます…
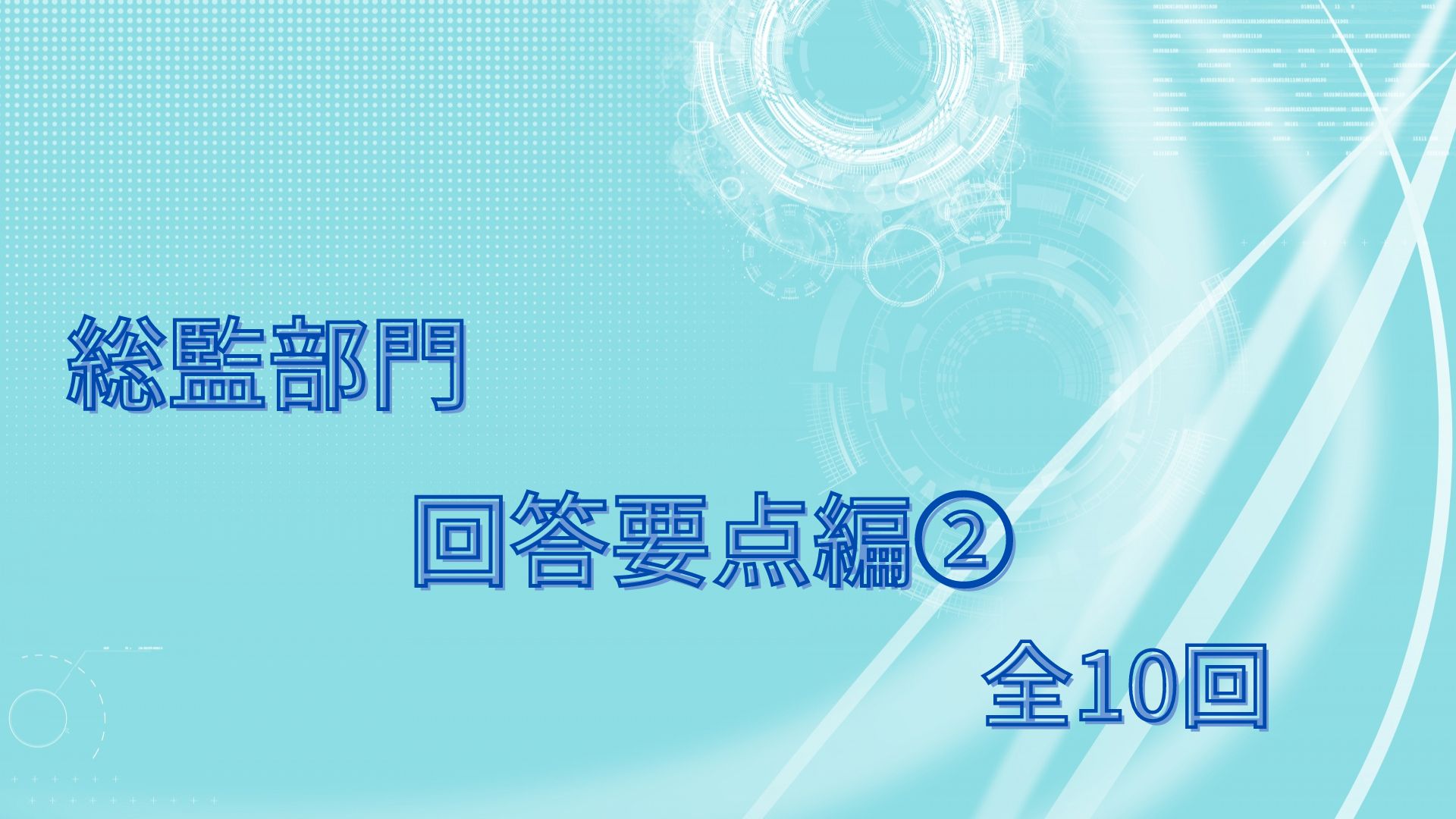

コメント