・2017年 必須 Ⅰ‐2 の復元回答(前半)は?
・取り上げる事業、過去、現在、将来の課題は?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士(建設部門)に続いて総監部門を取得した体験をもとに復元回答を発信していきます。




総監 必須 Ⅰ-2 2017年 復元回答(前半)

今回は、2017年 必須 Ⅰ‐2 の復元回答(前半)をお見せします。取り上げる事業、過去、現在、将来の課題を抽出しています。
復 元 回 答
(1)私が取り上げる事業の内容
①事業の名称と概要
本稿では、○○県内の各市街地における集合住宅整備事業を取り上げる。事業の対象範囲としては、デザインビルド方式による建設事業の請負である。建物の資産運用の提案から行う。発注者側で事業可否判断をし、当社側でも概ねの予算、工程が合致すれば、詳細設計、請負工事契約、施工の流れとなる。
私の立場は、積算部のリーダーで、メンバーをまとめる他に、事業全体を見渡す役割を持つ。具体的には、需要予測から建設候補地の選定を行う。また、候補地の法規制や地形の制約条件から、建設物の最適な規模や形状の提言を行う。コスト統制の必要性から、基本設計方針や概略の施工計画の策定も行う。
②事業の目的
既成の、あるいは今後市街地化するエリアでの集合住宅整備により、コンパクトシティ化に寄与させるのが目的で、表1の③の地域活性化に該当する。
③事業の成果物
基本は、鉄骨造の建築物で、ファミリー型の住居30~40世帯分と、1階は商業用テナントの構成である。地域の需要や規制によって変動はあるが、概ね8~10階建となる。4月以降に入居やテナント運営を開始することから、3月竣工であることが多いが、テナントの意向により、工期を早める要請を受ける事もある。
(2)持続可能性の観点からの課題
①過去の課題
1)個人裁量への依存大
以前は、設計・施工担当者の個人差による成果物のバラつきが散見された。これは、当時、手順書や標準図が整備されておらず、担当者の個人知に依存する部分が大きかった。また、都度ゼロベースから検討する事を繰り返していたため、労働生産性も低かった。
2)雪害による労働災害の頻発
雪害に伴い、事業場内での工事車両との接触事故やスリップによる転倒事故が頻発していた。雪害に対する緊急時の組織体制が整備されておらず、除雪の初動対応が今よりも遅れていた。また、発生の原因として、安全規格であるOHSAS18000の認証取得前であったため、組織的なOHSMSの運用が充分に機能していなかった。
②現在の課題
1)人材不足による工程遅延
東京オリンピックの開催が決定されて以降、首都圏ではオリンピックの関連事業が次々と着工している。この結果、○○県内からも首都圏へ協力業者が流出しており、人材不足が顕在化してきている。この結果、契約工期内の竣工が難しくなってきている。
2)遠隔現場に対する管理不足による不具合の発生
従来、本社のある○○県○○地域での事業が中心であったが、エリア拡大とともに○○、○○地域といった遠隔地での現場が増加してきている。遠隔現場の場合、店社からの管理が行き届きにくくなる。この結果、品質不良や労働災害、環境トラブルなどの不具合事象が生じ易くなる。一方、店社パトロールの頻度を高め、管理体制を強化しようとすると、店社側が人材不足に陥るという二次リスクが生じる。
③将来の課題
1)高齢化進行や世帯人員の縮小による空室率増加
現状のプランでも、車いすの利用を想定した水廻り寸法確保や床段差解消といったユニバーサルデザインに配慮している。しかし、さらなる高齢化の進展により、生活サポートを必要とする高齢者が増加してくる。 また、離別、死別、少子化、非婚晩婚化などの要因により世帯人数が縮小し、単身世帯が増加してくる。このような人口動態変化により、年々、空室率が増加する。この結果、発注者の事業採算が悪化していく。
2)環境負荷の増大 省エネ技術の急速な進展に伴い、現時点では最新の建築設備機器であっても、将来的には社会の省エネ要求水準に合致しなくなる可能性がある。また、清掃や定期点検などのメンテナンスが充分でないと、設備のエネルギー効率が低下しCO2の排出も増大する。計画的な設備のメンテナンスや更新を考慮する必要がある。
復元回答後半につづく…
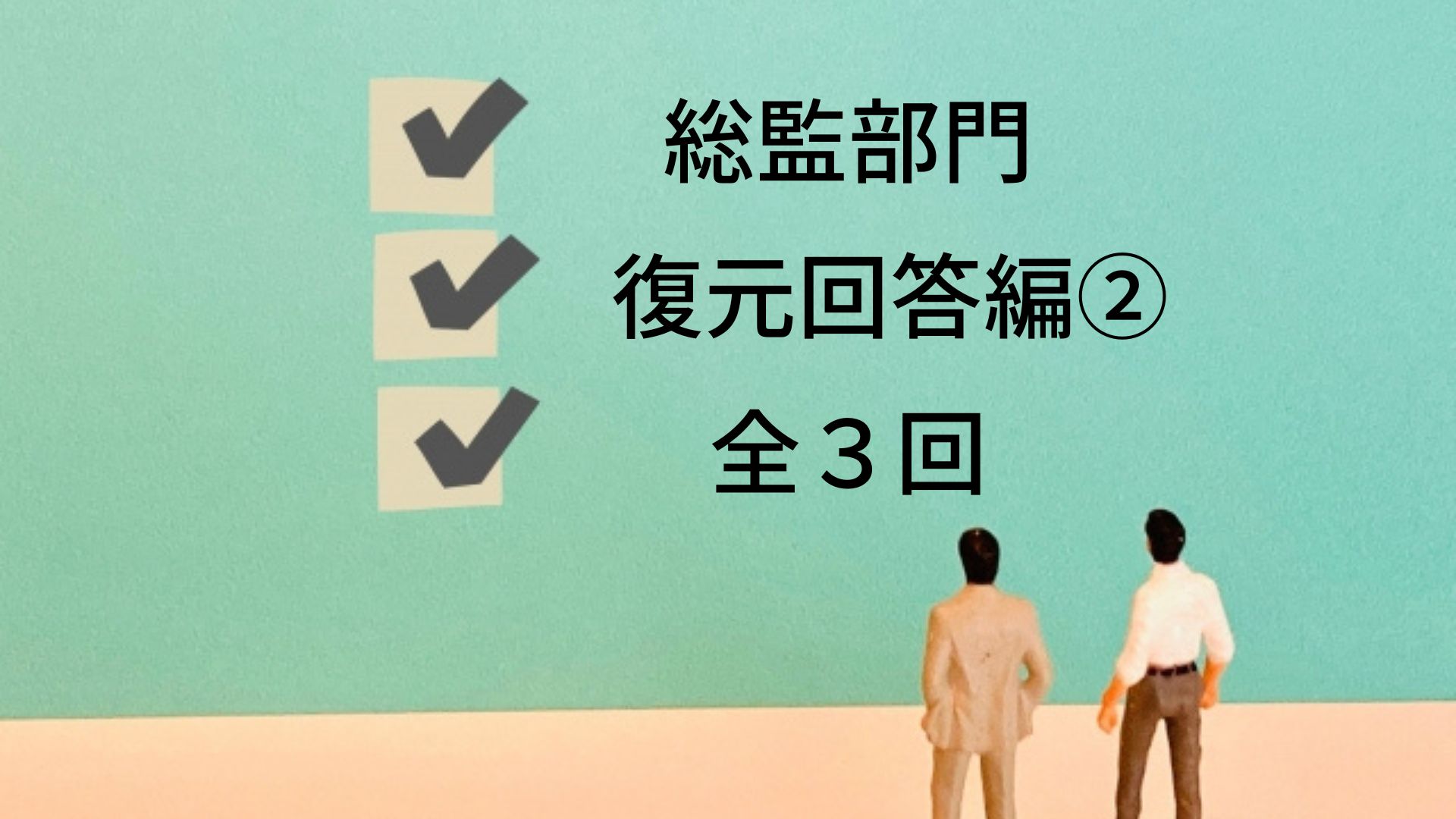

コメント