- 2017年 必須 Ⅰ‐2 の復元回答(後半)は?
- 現在と将来の課題解決は?
- 5管理はどう回答している?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士(建設部門)に続いて総監部門を取得した体験をもとに復元回答を発信していきます。



総監 必須 Ⅰ-2 2017年 復元回答(後半)

復 元 回 答 (その2からの続き)
(3)現在の課題への方策
①課題の選定とその背景
ここでは、人材不足による工程遅延を取り上げる。組織内部における制約として、設計・積算・施工スタッフの増員は不可で、金銭の追加投入は最大でも工事費の2%が限界である。外部の事業環境としては、東京オリンピックの開催決定前の8割程度しか協力業者の人員確保ができない状況である。
②方策とその際の事業の状況
経済性管理:擁壁や水路構造物のプレキャスト化、内外装の二次製品化、鉄筋のユニット化などを検討する。これにより、現場作業が縮減され、人材不足に起因する工期遅延を抑止できる。一方、この変更により直接工事費が上昇しトレードオフとなる。ここは、工業製品による安定品質につき維持修繕費の低減、また、工程短縮に伴い仮設維持費や現場職員経費が圧縮できる副次効果を加味し採用を判断する。
安全管理:プレキャスト化、二次製品化に伴い、部材が大型化し、搬入や設置の際の労働災害発生が二次リスクとなる。対策として、OHSMSの一環で閑散期に安全大会を開催する。その際、過去の具体的な労災事例を説明するといったリスクコミュニケーションにより、協力業者のリスク認知を促進する。
社会環境管理:現場での産廃やCO2排出抑制となり相乗効果となる。
(4)将来の課題への方策
①課題の選定と顕在化による影響
ここでは、高齢化進行や世帯人員の縮小による空室率増加を挙げる。影響として、発注者の事業採算が悪化し、地域活性化の観点でも負の影響が生じる。
②方策
生活サポート機能が付与されたサービス付き高齢者向け住宅へ現状の住居から用途変更を行う。1階の商業用テナントは、共用の談話スペースや機械浴室、運営管理者用の事務所スペースとして利用する。
③現在から検討、実施すべき方策
経済性管理:将来の用途変更に伴う改修コストを抑えるため、間仕切りの可変性や、スプリンクラー配管や機械浴室の給排水配管などの将来用配管を先行しておくことを検討する。
情報管理:二次リスクとして、間仕切の可変性や先行配管などの設計・施工情報を紙面による図面保管のみに依存していると、情報紛失する可能性が出てくる。対策として、BIMモデルを活用し、設計・施工情報を一元化した情報管理を行う。加えて、竣工後の定期点検や補修などの維持管理情報も併せてBIMで一元管理化し、施設管理の効率化によるLCC低減も図る。
人的資源管理:三次リスクでは、BIM活用人材の不足がある。BIMによる設計や施工モデルの活用度を高めるための教育訓練計画を立案する。 以上
次回以降、直近5年の試験問題と回答要点へ…
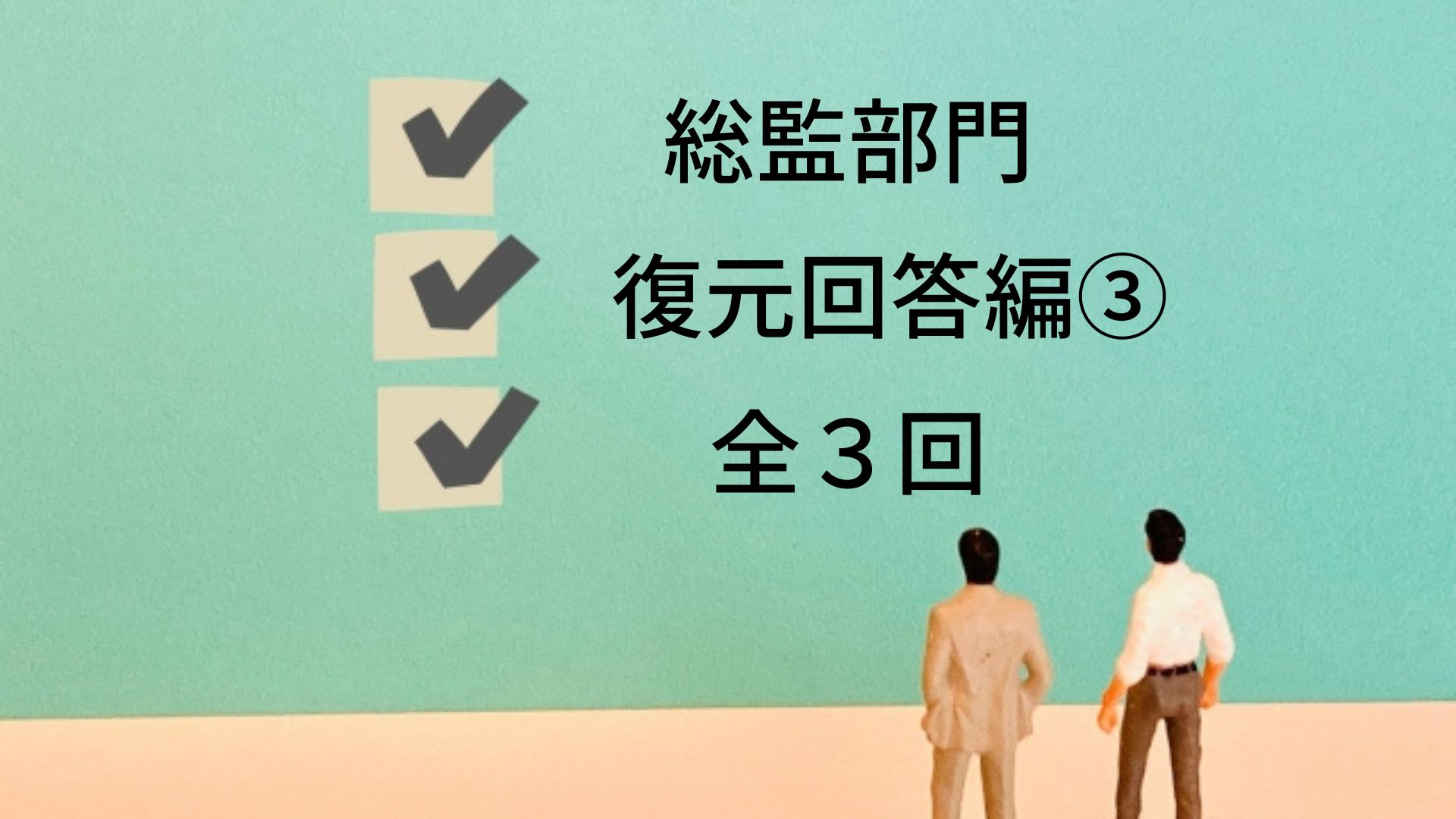

コメント