・自身の業務を試験の回答としてどの様に表現する?
・出題テーマごとにリスクや対応策を考える必要ある?
・試験本番で、回答の骨子はどの様にまとめていく?
社会人になるまで技術士の存在も知らなかった、一級建築士のKayが技術士(建設部門)に続いて総監部門を取得した体験をもとに傾向分析や対策を綴っていきます。



骨子ネタの作成方法

総合管理技術としてリスクマネジメントを採用すると分かれば、次に骨子ネタ作りです。当時、私は以下の項目に沿って自己の業務を整理しました。
『放っておくと将来〇〇となってしまう』⇒リスク
『だから◆◆策を行う』⇒対応策
『◆◆策を行おうとすると△△が損なわれる』⇒トレードオフ
『◆◆策をすれば、新たに✕✕の懸念が起こりうる』⇒二次リスク
『◆◆策をしても◇◇だけは解消されない』⇒残留リスク
前編で書いた様に、実際の試験では、様々な表現で問いかけられますが、その多くは上記のいずれかに当てはまります。ぜひ、ご自身の業務を当てはめてみてください。専門外のヒトにも分かりやすいシンプルなモノがむしろ良いと思います。
私の事例で…

私の骨子ネタを例に挙げます。『建設部材のプレキャスト化、ユニット化』という王道的な骨子ネタがあります。これは対応策なので、上記の◆◆に該当します。残りの項目も当てはめていきます。
リスク〇〇⇒主に人材不足、工期遅延など
トレードオフ△△⇒初期に集中的な検討負荷を要すため専門スタッフ必要(人的資源管理)
二次リスク✕✕⇒部材重量化に伴い楊重機械も大型化し重大災害リスク(安全管理)
残留リスク◇◇⇒現場作業は軽減・簡略化するが取付け作業工程は必要(経済性管理)
相乗効果□□⇒現場での産廃やCO2排出抑制になる(社会環境管理)
それぞれの項目には、他にも延々と考え付きますが、キリがないのでこの辺にしておきます。
5管理をバランスよく書いたつもりです。
ただ、情報管理だけがありませんでしたので…
例えば、トレードオフで専門スタッフ必要(人的資源管理)としましたが、
円滑なスタッフ育成のために業務手順書を整備(情報管理)
…などが挙げられます。これなら、業種問わず使えそうですね。
本番試験での使用法
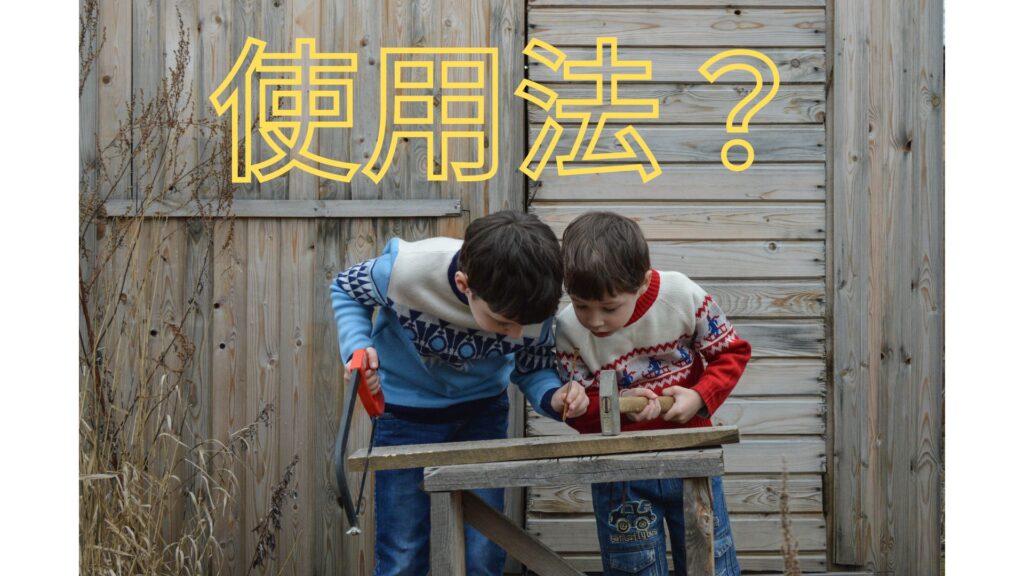
そして、本番試験での骨子ネタの使用法です。
毎年の出題テーマごとに、それぞれ異なる新たなネタが必要だとは思いません。というより、現実的に本番でゼロベースからネタを考える時間はないと思います。上記の様な汎用性の高い骨子ネタを用意しておいて、出題テーマや設問の趣旨に合わせてアレンジし紐づけるイメージです。実際に、姿かたちを変えつつもこのネタでほぼすべての過去問題を乗り切っています。
次に回答順序です。大問(1)から順次回答していては、用意していた対応策ネタがうまくハマりません。まずは、対応策の設問に着目してネタをハメるのです。そこから、逆流して出題テーマに合う形でリスク(あるいは課題など)を設定します。同様に、二次リスクやトレードオフも設問に応じて設定します。これらと矛盾しない様に、最後に適切な自分の事業・プロジェクトを取り上げます。
例年の試験問題文に「論理的なつながりを重視する」とあります。論理的につながりがなければ、得点になりにくいということです。骨子が埋まったら読み返して論理的つながりをチェックしてください。問題なければ、答案用紙に書き込んでいく流れとなります。
まとめ
・自身の業務を上記の流れに沿って整理してみる
・汎用性の高い骨子ネタがあれば、あらゆる出題テーマに対応できる
・本番試験では、最初に対応策をはめ込んで、逆流してリスクを設定する
次回…



コメント